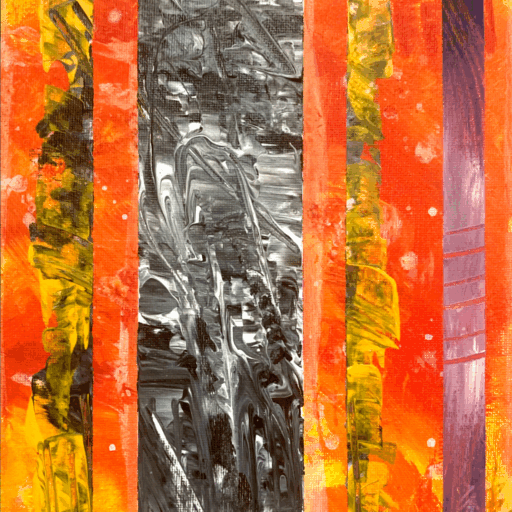ぎぃ、ぎ、規則正しい異音を乱すように「ッへぢゅ」くしゃみをひとつ。胸元に視線を落とせば慎ましいつむじがほよほよと。小ぶりな頭を手の甲で柔らかに撫でて、ぴんと立った耳を摘む。一口だな、とか。安心して眠っていてほしい人を、安心させる方法なんてわからなくて、いつかどこかで見た誰かの保護者を必死に思い返していた。優しく抱いて、緩やかに揺らしてやるといい、はずだ。だから首から下をふわふわの毛布ですっぽり包んで、膨れたのにずっとちいちゃくなった女を膝に抱えて安楽椅子に腰掛けた。自分よりも、見上げるほど大きな気がしたのに。手も、耳も、頭も、全身そのまま、やっぱり一口だな、なんて。
「ぴぃ、ふひゅ〜」
「んふ……ひはッ、くく、くへへ、ひ〜〜」
起こしちゃなんないから、笑っちゃなんなくて、それが余計に面白い。どっから鳴ったんだろ、かわいー。ぴかぴかの女は、男の腕の中でも眩しかった。押し付けられた頬が驚くほど熱いから、火傷させてくれって願ってみる。
「ニンゲンってのはこうなンだなあ」
からん、と口に出してみて、違うなと思ったけど、男には何が違うのかわからない。女ならわかるだろう、わからなくても、考え方を知っている。男には暴力しかないから、女の理知的な部分に全幅の信頼を置いていた。女の睫毛が震えている。たぶん、目玉がぐりぐり動いているから、夢を見ているんだっけ。女をゆっくり抱えなおして、それから、どうしていいものか困り果ててしまった。男にとって、夢とは恐怖だ。空虚な世界にぽつねんと、自分だけになって、水の一滴さえないことを突きつけられるのだ。男は女の安寧を守ってやりたくて、起こすわけにもいかなくて、笑ってしまいそうになった。あの脆い生き物を護ってたニンゲンはどうやってたっけ。
「ちりちり、燃える、灯火の子。稚いオンナノコ、えーと、大きなベッド、天蓋の向こう、おやすみと一声」
床の軋みよりもささくれた質感の声で、お世辞にも流暢とは言えない子守唄の紛いものを吐く。男には誰かの庇護下にいた記憶なんてないから、遠い記憶の文章をそのまま誦じるしかできなかった。縺れる舌を大袈裟に動かしながら女の額に頬ずりしようとして、はたと気がついてやめにした。ドアの隙間から、濁った目の老婆が睨んでいる。深い色の毛足の長い絨毯に埋もれながら、恨みがましく。羽虫が皮膚の余った顔の上を歩き回っている。
今日はまだこの部屋にしか用はなかったのに。準備をしていなかったから女に選んでもらった革靴が汚れてしまった。男はなにも癇癪持ちなわけではない。ふたりの真実は単純で、過失は老婆にのみある。馬鹿丸出しの金切り声のせいで、男の精一杯の言葉たちは女に聞き取ってもらえなかったのだ。男の悲しみは言葉が伝わらなかったこととは全く別のところにあった。女が眉をほんの少し下げた、男は胸に走る痛みを無視しなかった。男は自分のことでさえ教えてもらわなければわからないほど鈍感だが、こと惚れた女に関してはいっとう聡い。その表情が騒音への不快感ではなく、男への愛情故だと正しく理解していた。誠実な男なのだ、風祐くんは。
「すやすや、眠る、灯火の子。いとけない、い、いはるちゃん。分厚い毛布、ひひ、俺の腕の中、おやすみ、はるちゃん」
廊下は厭きるほど豪奢で、整列したシャンデリアが煌々と輝いていた。けれど老婆の目はぼんやりと暗く、憎悪を浮かべた形相とは裏腹に意思などありはしない。羽虫はとうに飛び去っていた。狭い室内は実に質素で、剥き出しの板張りの床が冷え切っている。カーテンだけはやけに質が良い、意地が悪い部屋。女のベッドは一番上の階にあるが、女に与えられたのはここだった。男の頭よりも一回り大きいばかりのはめ殺し窓の前、座面にひびの入った安楽椅子こそ女の領域だった。たった半月、主人をなくした部屋の電球は切れている。不意に走る電光が男の凹凸だらけの面を強調していた。
女を貰い受けてからというもの、男は随分と艶やかになった。かえるの化け物と謗られる貌に変わりないが、広い口を薄く縁取る唇だとか、癖のある髪を掛けた丸い耳。なによりもその眼が、じろ、と窺うように動くのをやめた。男はもうずっと、女しか見なくなった。他人への無関心と対比するような激情をちっとも隠さない、いっそ無防備とも言える態度は、内側からの湿っぽい香気を纏って男を存分に彩った。
「ん〜、ゔぅ」
轟く雷鳴に眉を顰めた女が僅かな唸り声をあげて覚醒した。気怠そうに息を吐いて男の鎖骨に頭突きする姿さえ幻のように麗しい。他意なく甘えて笑う女は、気品溢れる顔つきがあどけなく見えるのだ。とろとろと微睡みながら男の腕を抱き寄せて毛布に埋まる。
「起きちゃったあ」
「まだよう。起きちゃいないわ……だから、ここにいさせてくださいましね」
男の胸に広がったのは嫌悪だった。血潮が搔き混ぜられている、既のところで飲み込んだ強酸が喉を焼いた。女が、願わなければならない人生を送り、それを今も背負っていること。風祐くんにできるのは、はるちゃんに翳るよろずのことを遍く殴打するくらいだ。閃光が駆け抜ける。残されたのは闇だった。薄暗い室内で、やっぱり女は咲き誇っている。額に口付けをした、それは祝福だと教わったから。男は安寧を願っている。
暗がりを受け入れたふたりきりのお屋敷で。
「はるちゃんは、ンと、あのさ、なんだろ、充電式?」
「食べて、エネルギーに変換してるから、発電式かしら」
「そっかあ」
「どっちがお好き?」
「おまえが」
女は下唇をきゅぅと持ち上げて眉間をくちゃッとした。弱者に成り下がった腑抜けだと見抜かれてしまった。灰皿で殴られたかつて、奴隷根性なんて血反吐と棄てた。飲むのは憾み、そうでなければ生きちゃいけない。女の血肉となった覚悟は、それは、理不尽なんぞに諂うためじゃなかったのに! なにより、こうも無様を晒した理由を今更に認識した怠慢に虫唾が走る。飛永怡陽の、並ならぬ執着の先、それは武力。いつだって蹴り飛ばしてやりたかった、どこへも行けぬ華奢な脚を上手に使ってみたかった。女が求めたのは、凶器、殺傷道具、そういうものだった。河津風祐があんまりに鮮烈なものだから、見誤ったのだ。軽々と抱えられた気がしてしまって、燃ゆる心臓さえ預けてしまいそうになった。慢心だ、恥晒しだ。あなたがいるからひとりで眠れる、なんて思ったのよ。誠実な男、すてきなひと、ここにいるの、わたくしの風祐くん。あなたの形を間違ったこと、それにも拘らず染みついたみっともない生存戦略を選んだこと。わたくしの贖いようのない罪禍だわ。
「ふゆ」
「なに、はるちゃん」
「どして、ないてるの」
「なか、せ、ないでよお」
肌を流れる涙の歪な跡が、男の醜さを知らしめていた。「どして」と訊かれたってわかる筈もない、なんたって初めてだ。ぼた、と女の眦を汚して血の気が引く。ぐっと顎を上げたら苦しくてもうだめになった。男は儘ならぬと訴えている、雷鳴さえ遠退く大声で、幼子のように。女は歯痒さを堪えながら男の血管のよく見える首筋を眺めていた。なんども深く沈む喉仏に噛みついてやりたくて、代わりに口付けを贈った。
「ひっ、ぃう……うえぇ、ッぎゅ、ひぁあ」
「ふゆ、風祐、あぁ、こまってしまうわ」
「ご、ぇな、ごめ、ぅ、はぅちゃ、いはる、ちゃん」
かわづの男がないている。嗚咽混じりの謝罪を顔色ひとつ変えずに聴いているガラス片の如き涼やかな女の横顔を、暗雲をさいた陽光が照らす。あてられた女はじん、と痺れる脳みそで考えて、男の両肩をとん、と押した。ぐらり揺れる椅子と視界の端に映る髪。あたたかな腕を自由にしてやった。
「われンな!」
銃声と紛う音を立てた男はびいどろの眼を白黒させて、信頼していたものに突き放されたみたいな顔で戸惑っている。女は真っ平な心持ちで、受け身がお上手ね、と思った。お先にと身を起こして地に足つけた女が男の胸倉を捻り上げて、なだらかに弧を描く額をがつんとぶつける。口角が上がっているばかりの表情で。
「俺、がわるい、ぜンぶ」
ぢゅぅ、吸ってみたけれど、必要なのは甘さじゃないから。女は薄っぺらい舌を味わって、半開きの口に押し返した。次いで、自分の重たい舌を捩じ込んでからぶちんと歯を沈めた。だらだら溢れる鉄錆の熱を流して、ようやっと納得いったのだ。男の首に手をかけて、嚥下のたびに広がる感触を愛する。脱力した男が崩れそうになっても追いかけて逃さない。頭を支える手で頸に爪を突き立てた。いまや窓外は晴天、室内の明暗を強める爽やかな陽射しは女の暴挙に気がつかない。羽衣の天女もかくやあらむという美女が、善人さえ眉を顰めるほどの人外じみた醜怪な男と、肌が粟立つほど清艶な血塗ろの口付けを交わしていた。
男は腰抜けになってしまって、ついた後ろ手で空を握っては大粒の涙を落としている。歯列の裏、頬の肉、怯えて縮こまった舌の付け根、隅々まで這う甘い肉に擦り込まれる血液は爛れそうなほどあつい。大好きなひとの味がする。口蓋にべったり張り付いた舌、そのむず痒い味蕾のざらつきさえ鮮明なほど、男の頭は冴え渡っていた。だからわかる。女の血潮の激る理由が。
「は、ンぅ、ッぢゅ、はぅ、ぁ、るちゃ」
「ッはふ、お黙りになって、無粋よ」
「ゎう、まっ、ぇ、ンぎゅ、まっへ」
「なぁに、なんだって言うのかしら。嫌とでも? 舌先三寸咬みちぎってその喉をぺしゃんこに潰してさしあげるわ」
「あいしてる」
男には本当にこれっぽっちも、場違いな告白なんてするつもりはなかった。ただなんだか、熱烈に口説かれた気がして、面映くなってしまったのだ。へら、と情けない笑みに呆気にとられた女は、口の端からどろりと伝う真赤な体液もそのままに愛しい男を抱きしめた。
「ごめンなあ、間違った」
「おあいこよう、ごめんね」
「俺もはるちゃんも、生きてンのにね」
「あっははは! そう、ふふふ、そればかりだわ!」
疵瑕などありはしないのに、あったとて、終いになるほど脆弱ではあるまいて。そんなことさえ、わかりゃしなかった。自嘲を過ぎ、交歓を経て、心臓の音を混ぜて微睡んでいる。ふと舌の痛みを認めた女は、口元にあった男の耳朶を食んで慰めとした。ふにふにと弄んで、ここも薄いのだと知る。
「くちあたり、いいのお?」
「おいしい」
「いひひ、よかった」
陽は傾きじりじりと身を隠していく。長く走り来たる光がなにもかもを無作法に染め上げていた。「あ」思わず声に出た音を女は拾わなかった。男は当たり前のことを理解して、それを当たり前だと認識した自分が誇らしくなってこっそり笑った。女にはバレているし、男もそうだろうとは思っているけれど。ともかく、腹落ちした。間延びした夕陽よりも赫赫たる女だからこそ、焦がれる熱なのだ。
嫋やかな指先で髪を梳かれながら、見開いたままゆめをみた。男の頭の中にいる女は熱源で、輪郭さえ消し飛んでしまうほど偉大で、また一人になってしまったと錯覚してしまうような畏怖の象徴でもある。けれど自分の手が、足が、真白に融けていると安堵を覚えるのだ。光こそが女である。眩い全てが女だ。男は自分の後ろに伸びる影にうっとりと口付ける。濃く深い、この影が、この闇が、女のそばにあることの証明なのだから。
「はるちゃん、はる、いはる、俺の御天道様」
「もっとかわゆい呼び方になさいな」
「飛輪」
男に、飛永という姓を教えたことはない。一族郎党皆殺しにして独り占めしたいと願うほど気に入っているということも、もちろん知る筈はずがないのに。背を駈けのぼる興奮に従って首筋に歯をあてた女は、理性に叛いて顎を閉じた。予備動作なく咬まれた男は「歯もちっこいンだなあ」なんて言って甘やかしている。
「やっぱり、とびきりすてきね。わたくしの王様」
「かわゆくするとどおなンの?」
「風祐。これ以上にかわゆい称えがあって?」
「ンなこと言ったら、いはるの上はねえだろ」
夜が近い。溜まった冷気に浸った身体は鈍く、このまま眠ってしまいたいような、怠惰に惹かれつつある。同じ温度の肌は至極心地が良いものだと悟ってしまった。女は世界を遠ざけようとする瞼を叱りながら、男の望みを叶えるために口を開いた。
「二つ上がって、最上階の一番大きな寝室。わたくしの整えられたベッドがあるわ」
美しく、淑やかな、たかねの女に齎されるもの。堂々誇るべき報奨。ただの一度も、乱れたことのない、潔白のベッド。
「わたくしのことよぅく抱き締めていて。そしたら、真ン中に置いてあげる」
寸分狂わず無邪気な声だった。ぱっと目醒めた男は沓摺に目を向ける。境界線、こちらは内であちらは外だ。それがどうした。死体はなにも見れやしねえ。女は死体を見やしねえ。抱き締めた、傷つけるばかりの手で強く。はしゃぐ女を落とさぬように酔わさぬように、間を持って歩む男は、見惚れるほど瀟洒だ。開け放たれた扉の前、くるり回って一礼を。
「さようなら!」
男の側頭葉は滾る絶叫を認めた。愛しい女はさざれの声で笑っている。重なってぐわんと視界がぶれた。途端に動き出した電気回路がふたりを飾る。女は意気揚々とシャンデリアの真下に躍り出た男にあわせて歌ってやった。蹴り飛ばされた死体の鼻が歪んでいようが、誰にも伝わることのない与太話だ。
階段を跳ねて飛ばして一番上。しっとりと足音を奪う絨毯を踏み締めて辿り着いた寝室の前で、あっさり踵を返した男を止めるなんて女にはできなかった。錠のつまみが表側についた扉を、赦す男じゃない。けれどね、風祐。
「ぐちゃぐちゃにしてやりたいわ」
男の髪で遊んでいた手を離して薄い唇に押しあてる。口付けを奪った指先でするり、パンプスの隙間に差し入れて、ぱちんとストラップを外した。やわらかく、つんと尖った爪先が顕になる。ほっそりと長い指に引っ掛けたそれを、全力で投げつけた。ガンッ、きれいな音が鳴った。エナメルのピンヒールが、両開き扉の中心に突き刺さって光を返している。
「……ひ、ひはは、ッへえ、へ、はは」
「あけてちょうだいな」
「ンぎゅ、は、ひはははっ! ひい〜っ、げほ、ぎ、いひっ、ンははははは!」
ただでさえでっけぇ声なのに、女を抱えたまま背を丸めて大笑いするものだからもう大変。女はちんまいお顔をぎゅむっと歪めて堪え忍ぶしかないのだ。耳を塞がないのは愛ゆえに。波が引かない男は咽せながら扉に駆け寄って、肺腑の制御を放棄したまま女に語りかけた。
「な、なあ! ひひ、い、はる、っはは、いはる! 蹴破ってえ!」
ぱちぱち瞬きして、にんまり笑顔を浮かべた女は、もう片方も脱いで素足を晒した。振り上げて狙いを澄ます。男は眼前に掲げられたつるりとした足の甲に目を奪われて、はわわとなった。一口でいけるな。女が深く息を吸って、ぴしゃりと落とした。生身ではあり得ない音がしたし、割れているのは取手よりも下だが知ったこっちゃない。
眼前に広がるは純白の寝室。中央には巨大なベッドがひとつ。顔をあわせたふたりは微笑む。躊躇わずに一歩、それから真っ直ぐ歩んで、飛び込んだ!
「きゃ、あは、うふふ、溺れちゃうわ!」
「まって、はるちゃ、見失うから! どこ、落ちてない?!」
ふかふか枕をぶん投げて、さらさらシーツに潜り込む。好き勝手に暴れる女は、少女と見紛うほど無垢に輝いていた。枕を叩き落としてシーツを捲って、隅っこでやっと女と再会できた男は、手早く捕まえて真ン中に転がった。どちらともなく額を擦りあわせて、確かめるように触れては、余す所なく口付けをする。歯が触れぬように気遣いながら肌の甘さを憶える男とは違って、女は不意に本気で咬んでは血が出る寸前ではっと我に帰る。そうして刻んだ歯形に涙目で口付けを落すのだった。矛盾した行為の感情は、傷つけてしまったなどという陳腐な後悔ではない。自然治癒力によっていずれなくなってしまう、儚いものを与えてしまった罪悪感だ。愛しいひとからの贈り物を、他でもない自分自身が消し去ってしまう男の惨痛を想うと、自然と視界が揺らいだ。
「はるちゃん、好き、あいしてる、いはる」
「風祐、おいでなさいな、んふふ、ぜんぶが愛しいひとね」
隙間なく触れていたかった。衣摺れなんかに鼓動を邪魔されたくなかった。背筋を辿って肋骨を数えた、互いの血管の色を比べて、視線を絡めれば舌もそうした。絶えず言葉を交わし、血も心も融かして混ぜた。静かに手を繋いで、笑いながら足を擽って、泣きながら頬を舐めた。耳朶から爪の形まで、あらゆる感覚で憶えた。口に含んだ指がどちらの何番目かだって間違えない。脳が蕩けたまま享受する痛みがどれほどの幸福かを思い知った。
「しあわせ、風祐がいるから、幸せよう!」
「おれも、俺も、幸せ、ずっとだ! いはるが、いてくれンならさあ、永遠だ」
穏やかな曙光が男の背を照らしている。望み通り乱れたベッド、纏わりつく気怠さ、健やかな寝息。なぁんだ、潔白に変わりないじゃない。
射干玉の髪に透ける火照った肌、吐く息はやけるほどの熱を孕んでいる。欲情することさえ烏滸がましいような、稀代の美しさ。女はそぅっと横たわり、ぐっすり眠る男の頭を撫でて抱え込む。散らばった長い黒髪が、純に白いシーツによく映えていた。