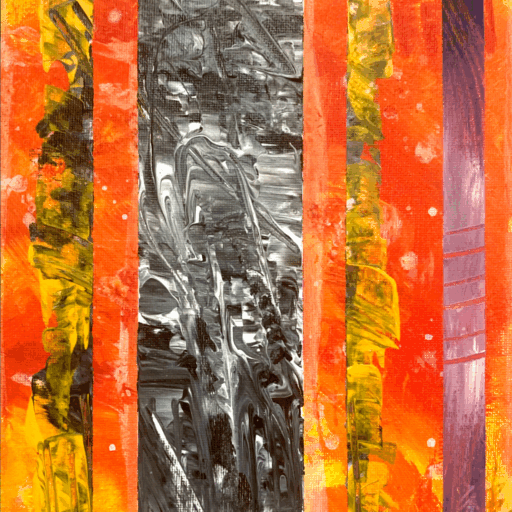小説 玄関 晟陽
つんと入れた切先をまっすぐに引く。うまくやりゃ、まんまるの珠がまろぶ。尾椎のおわりの骨だ。腑を抜いて、丸のまま皮を剥ぐ。脂肪で滑るから、木綿の手拭きで押さえるといい。肉は存外に柔い、落ちる寸前の桃によく似ている。それからこういう手合いは雑にすると祟るらしい、肉を削ぐ前に上下を断つのはよしておくべきだ。皮は塩で揉んで肉と一緒に、内臓は中身を出して酒で洗って使う。骨も出汁を取ったら粉にして、脳みそと血で溶いて飲む。全てを腹に収める。
「おぉい、雲来! おらんのかぁ?」
額に脂汗が滲む、拭うとかえって汚れがついた。ぬめる手が汗か血かもわからん。茹だるほど暑い。床の間にウジがわいた。いつでも蝿がじーんとうるさいが、捌いている間は嫌に静かだ。この肉は、あらゆる生命に嫌われている。尾骨を離そうと包丁を振り上げたが、握り込めずに狙いが外れた。骨と柄に挟まってばきと爪が割れる。怪我をすると痛い。
「雲来、出てこぉい、おゆきも待っとるぞぉ!」
下から順に別けていく。頭までやるにゃ二日は掛かるだろう。時間と食い物は腐るほどに。海から揚げて数時間、氷で囲っているわけでもなしに、触れるときんと凍える。陽にあてると焼けるが、陰れば冷える。食えばどうなる、何れ知る。目玉は依然として、澄んだまま俺を映していた。顔掛けでも用意しておくべきだったか。妙に膨れた肉を割くと縮こまった脚が出てきた。どうにも獣のような。皿に並べた腑をひとつ手にとる。こりゃ、子宮か。なんにせよ、食うだけだ。
「明日にでも、また来るからなぁ」
酷く喉が渇く、真水も酒も唾液さえも、塩っ辛くていけねぇ。ぐらと視界が振れる。半身を整えたら一休みしよう。腹が減った。どこもかしこも脆くて気を使う、粗野に扱えば穴だらけの骨が砕けて肉に刺さる。洗って破片を集めるなんて考えただけで鬱々とする、余計な手間はかけたくない。
柵にとった背肉から脂を外す。薄く切って、塩を振ったら少しおく。そのあいだに、桶に溜まった血を湯呑みに掬って囲炉裏の縁に埋める。温まるまで待てば肉の臭みも抜けているだろう。燻る炭に手を翳せば、痺れのかわりに痒みを得る。指先が霜焼けになっていたらしい。饐えた臭いが鼻につく、蝿が何度も視界を横切る。今も、ほら、いまも。
がぼ、がぼ、人の溺れたような音にはっとする。血がふつふつと煮えていた。熱い湯呑みを片手に流しに戻る。一回り小さくなった肉をそっとつまんで、口に放った。
「ぐ、げぇ……ん、ぐぅ、ぇほっ」
歯を使わずとも潰える寒天よりもやわい肉、舌にへばりつく腥い脂と、咽喉を焼く異常な甘み。薄荷に似た刺激が鼻を抜ける。胃が痙攣して迫り上がってくるのを、何度もすんでのところで飲み込む。一度目にあった塊が、二度目には砕けている。三度目には胃液と区別もつかんほど溶けて、四度目には舌に乗る前に降りてった。目の前の切れ端と、その奥の肉塊を見て気が遠くなる。吐瀉物の味に慣れるのは何度目になるだろうか。
一枚、口に放った。
未だ沸き立つ血で流し込む。味も臭いもない、気が触れそうだ。熱とともに、何かが染みていく。脳の真ん中がぷちと弾けた。二度とは戻らぬものがおそろしい、恐ろしささえ消えていく、赤い血潮で押し流す。
「ごちそう、さま、おぇっ」
薄く削いだとはいえ、大皿いっぱいに盛った刺身を平らげてなお、腹は満ちぬ。目が合う、じっと俺を、見ている。馬鹿になろうと湯呑みに酒を注いだ。残った血が沈む、深く。底なしだ。覗けば水面に俺が映る、俺を見上げている、目が合う。濁ったそれを飲み干した。
さむい、全身を撫ぜられるような悪寒から逃げる術はない。囲炉裏の灰に手を埋めても、炭を握っても、痺れるほど凍える。割れた爪から血が垂れた。
「雲来、雲来! おまえ、おまえだけは、ころす、殺してやる」
痛みは熱だ。指先の救いに縋って、爪を剥いだ。
「るりをかえせ、瑠璃、るりを、まだ、子供だった、幼い、おれ、おれのるり、返せ」
ぼたと滴る、灰が黒く固まる。吐き気が止まらない。蝿がうるさい、どこに、どこにも見えぬ蝿が、じーんと飛び回って俺を苛む。ぐちと傷を抉る。さむい。
「こ、ころしてやる、必ずやおまえを、おまえ、瑠璃、るり、死んだ、殺された! 返せよ、返せ、かえせ!」
流しに走って湯呑みを引っ掴む。つるりとした蒼の釉薬を血と酒で隠した。温める時間も惜しい。握り潰した炭を入れるとすぐに沸いた。黒い欠片が浮いている、気にも留めずに傾けた。じゃくと噛み砕きながら嚥下する。腹の底からかッと火照り、脳が鈍間になっていく。自然と意識がおちた。
「死ね」
夢を見た気がする。この暗がりの部屋にウジがわく前の、花の匂いがしていたころの、寒さに怯えずにいられた一日の、そういう夢を。
寝たまま髪をかき上げる。ざらと灰が散らばった。転がった湯呑みを拾って中を見ると、縁から底まで少しの水気もなく空だった。起き上がるのが億劫だ。天井に向きながら意味もなく畳の目をなぞる。数えるわけでもなく、ただ爪の甲を凹凸に擦った。微かに、蝉の声がする。
「雲来、今日はおゆきもおるぞ、返事だけでもよこせぇ」
そういや今年は風鈴を吊るしていない。紐が切れたんだったか、割れたんだったか、両方だったような。空気が滞留している。重く、その場にある。蝿の飛ぶのも、俺のため息も、戸を開けるのも、全部が下の方に閉じ込められている。息苦しくてあくびが出た。
「雲来さん、あたし、あたしね、待ってますから」
肺がぐっと膨らむのがわかる。こんな惨めな身体の中で、内臓は俺が生きるために粛々と役割を全うしている。当然のことだ、それがどれほど得難いか、よく知っている。臓物は腐りやすいという、ひとりでに凍りつくあれも、いつしか饐えた臭いを纏うのだろうか。食わねば、どうなろうとも。だができればこれ以上、えずく要因が増える前に。
「ねえさんのこと、忘れらんなくったって! 一緒にいられるなら、あたしそれでいい。雲来さん、いいんです」
根を張りたがる足を引きずって頭から水を浴びる。口に入る水がからい。しとどになってやっと目が覚めた。もう苦しくなかった。朝飯は何にしよう、よりどりみどり、子宮と肝臓にしよう。血の煮凝りのような肝臓を角を立たせて切る。弾力のある子宮は細長く刻んで鍋に入れた。布に包んだ骨も浮かべておく。酒と水と塩で煮込みゃ大概のものは食える。
「おゆきもこう言っとる、いつまでも拗ねとらんで、早よぉ出てこい」
満たされた鍋を囲炉裏に提げて、さきに肝臓をつつく。ぬろと舌に乗る、水羊羹にも似た感触。仄かに甘い、ような、無味無臭だ。血に近すぎるのかもしれない。すぐに溶けてなくなる。肉より幾分食いやすいが、やはり味のしないものは気味が悪い。手早く腹に収めると、ちょうど鍋が煮えた。けぶる湯気が肺に流れる。薄荷よりも濃く、青い。
「ぅ、げっほ、ぉえ、ごほっ」
白濁した汁を啜ると咽せるほど塩辛い。無味が恋しい、一切れくらい残しておけばよかった。沈んだ内臓をおそる恐る口に運ぶ。ふつと潔く噛み切れるそれは、花の匂いがした。全身でもって拒絶している。今すぐに吐き出そうとする本能を捩じ伏せて、よく噛んで飲み下した。耳鳴りがする。脂汗が噴き出す、底冷えする恐怖が背を撫でた。手を止めてはならない、噛んで、飲んで、血肉とするのだ。俺の全てを作り変える。俺は食事をし、俺は自決をしている。手足が震える、落とした欠片も残さず食う。爪先がぎちと丸まって固まった。舌を孔だらけにして得た満腹感は吐き気がするほど悍ましい。
「雲来さん、きっと、きっとですよ、迎えにきてね」
たすけてくれ。鍋の底からのぼる泡が、その破れる音が、俺をこの世に留めていた。瞼の裏に張り付いた視線が縁だ、追えば冥土を辿るだろう。寒気がする。蝉が歪んだ声で喚いている、うるさい、うるさい。
「今日はかえります、ゆっくりやすんで、あすはお返事してね、そしたらあたし、泣いて喜びますから」
丸めた背に鋭い痛みが走る。耳を塞いでも逃げられない、うるさい、うるさい。箸を炭に突き立てた。鍋が沸いている。びちびち、脚が跳ねる。焦臭い。箸を持ち上げたら炭が引っ掛かっていた。噛み砕いて、舌が爛れた、青い匂いがする。黒く燻る箸先を耳に刺す。じわと鼓膜が焼け落ちた。蝉の、うるさいのが、ずっと、頭蓋の内側でのたうつ。胃がひっくり返って喉が塞がった。
あ、俺の声か。
「ぎゃあ!」
耐え難い痛みで飛び起きる。囲炉裏端で寝ていたらしい、炙られていた肌がぐずと崩れた。流しに転がり込んで血溜まりの桶に腕を浸した。煙が昇る、鉄錆の匂いがした。肉の隙間から薄汚れた骨が覗く、血が染みていく。足りぬ。火傷が広がっていく、あぁ、ほら、もうここまで。目が合う。俺を見ている。開けっぱなしの腹に腕を捩じ込む。掻き混ぜられた肉がどろと垂れる。暴力的な熱が、もろい肉の鋭い冷に殺される。深く息を吐いた。血の気がひいた手を頬に当てる。ぬると滑る、口の端が解けていた。汁類には苦労するだろうな。
「きいた、聞いたぞ雲来、おまえ、お前は!」
纏わり付いた血肉を舐る、爪の間、指の股、晒した骨の凹凸。塩辛い、甘ったるくて、爽やかだ。ぐちと粘り、赤い糸が張る。毛繕う畜生のように、飢えを凌ぐ忌子のように、ただ夢中になっていた。
「おれの、瑠璃を、るり、代わりにして、かわり、お前のしんだ、し、死んだ女の、代わりに! か、かえってこない、返ってこない、かえって、かえせ、返せ! 返せ!」
喉に絡む、咳をすればごろと鳴った。爪を立てて、千切った肉を口に運ぶ。腹が減った。筋に指を引っ掛けて外す、舌の上でとろける脂を飲んで、奇形の内臓に齧りつく。花の匂いが肺に満ちる。冷たくて、甘い、痛みが鈍る。脳みそがずくと疼いた。心臓の音、拍の衝撃が全身を駆ける。膝が笑う、視界がぶれる。頽れて、顔を埋めた。抱き締めるようにして寄せた死骸を貪る。壊れた骨が刺さっても、痛みはなかった。味のしない体液を啜り、寒気がする肉を食む。恐怖に屈した精神は狂気でもってまともであろうとした。
「お前の女は死んだ! おみつは死んだ! 死んだ! おみつも、おれ、俺の、瑠璃も! お前が殺した! 死ね、しね、殺してやる!」
殺せ。耳障りだ。肺腑の膨らむのも、血潮の巡るのも、歯の打合わすのも、もうたくさんだ。這いずりながら柵と臓物を並べた皿に手を伸ばす。戦慄く指がひっくり返した。蹲って両の手で掻き集めながら口に詰める。床にへばりついた破片にも舌を押し付けて、少しも取り零さぬように。
「あ、あ、あんた! 雲来さんが、なにしたって言うのっ、かえって、かえりなさいよ!」
小さい爪の、細い指に歯を立てる。ぱちと割れて、あっという間に骨まで砕いた。尖ったそれぞれが胃に刺さる。血反吐が上って、血管と、神経と、筋と、骨と、肉と、皮と、下りてった。血の深く溜まった桶に顔面を浸して喉を潤す。
「あいつは、瑠璃を殺した、俺の、おれのかわいい、幼いるり、瑠璃、自分の女を殺したみたいに、るりも、はは! うはははは! おまえも、お前、殺されるさ、ばけもの! 化け物に!」
今に見てろ、その目玉さえ、噛み潰して腹の底だ。脊骨を折って、肋骨をもぎ取る。肺の片方を毟って、心臓を曝す。喉仏をくり抜いた。頭蓋を抉じ開けて、脳を割る。
「やめて、やめてよ! ねえさんは勝手に死んだの、首括って、薄情者だわ! 雲来さんが、どれだけあの女を愛していたか! そのるりだって、ほんとはあんたが殺したんじゃないの?!」
なんと、静かな。血潮は留まり、心の臓腑はきんと凍てつく。視界が揺れる、滲んで、鮮明に、俺は泣いている。今更になって、これが情とは言うまいよ。
「ああ、あ、死ね、俺たちは、愛し合っていたのに、縄を、化け物、なわ、縄を、切ったから、瑠璃は! 沖まで、し、死んだんだ、殺された! あのこはおさない、幼いから、餌だって俺が、俺が、面倒を、瑠璃は永遠だったのに!」
暗い、ここはもう、二度と陽の射すことはない。いずれ大嵐に、さらばえるばかりだ。
「なんの、話をしてるの、縄だ餌だなんて、人間じゃないみたいに」
「だまれ、黙れ! お前もおれを、俺を馬鹿にするのか、に、にんぎょ、人魚はいるんだ、おれの瑠璃! こわかったろ、いたかったろ、俺は正気だ、おれだけが、俺が本当だ、殺す」
「きゃ、あ、ぎぃ、うぅ、ぐぇ、ゔ、らいさ、うんら、ざん、ぐぎっ」
「は、はは、ひっ、は、ははは、おまえのせいだ、はは、雲来、雲来! お前の、せいで、死んだ、はっ、は、ころす、殺す、お前も! 殺してやる!」