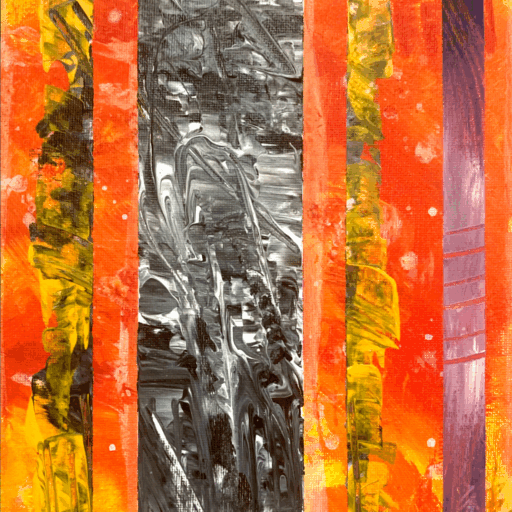小説 玄関 晟陽
「荒巻くん、わたくしね、怒ってるのよう、どうして女の子と連絡先を、交換なんてなさるの、わたくし以上に愛らしい子がおりまして?」
つんと尖らした唇でつとつと文句を言う女。まだるっこしい喋り方で、人を待たせること当然としている。ちまこくてやわい、過保護に尊重されることに慣れきった女。長い黒髪をしゃらしゃら流して、伏したまつ毛が頬に影を落としている。窺っているつもりになって、心底じゃなに一つ揺らいじゃねぇ。怒ってる、なんぞ。それが本当だったらどんなにいいか。オレを気にしてるつもりになってら。握りしめたこの拳の、内がどうなってるかさえ気にも留めないくせに。痛みに慣れちまって、情けねぇや。
「あ? オレが好き好んで女と連絡先の交換なんかするかよぉ。たまたま用事で必要だっただけだ、個人的な話はしてねぇ」
「本当に? 見せらりるかしら、わたくしに、いま」
「ハイハイ、見せらりる、ほらよぉ、勝手に見ろ」
「きゃん! 投げないでくださいまし、乱暴者なんだから」
下からゆるく放ってやった。子犬のような悲鳴をあげて携帯を受け取って、まっすぐ削られたツヤピカの爪をぶつけながら必死にカコカコ弄ってメールを見てる。外では小さな氷粒がぱららと降っている。晴れてんのになぁ、なにが気に食わないんだか、わざわざ地面にぶつかりに行くなんざ。バカみてぇ。あー、バカなら落っこちちゃこねぇか、高いとこ、好きだもんな。どれもこれも積もるばっかで、嫉妬のつもりだ。お上手な女。そのくせ嘘は吐かねぇもんだから厄介が極まってら。言葉までも、お綺麗に取り繕っちゃくれんかな。
「あ、荒巻? いいのか? アレ」
さっきまで美少女だなんだと騒いでた北原が、今じゃ怯えたように聞いてきた。人を指差すな。
「ごめんごめんごめん離して自分差し指になっちゃう」
「うるせぇな。いいんだよぉ、そのうち満足して戻ってくる」
「いってー。や、戻ってくるのは当然として、見られていいのか?」
視線の先ではやけに真剣に、底なしの黒目をくつくつ煮やしている。芝居掛かった女だ、幼馴染でもなきゃ、これが本当に素直な姿だなんて信じらんねぇだろう。オレがこの女を、理解した”つもり”ならどれほどよかったか。すこしも間違っちゃいねぇから嫌んなる。
「いいから渡してんだろ。それに、アイツは気になるもんしか見ねぇ。その女とのメール以外に手はつけねぇよぉ」
別に吠えるほどのことでもねぇや、滿月はそういうヤツだ。余計なもんには一切興味を示さねぇし、欲しがりもしねぇ。気になることだけ気にして満足する。だから、携帯なんか渡したって問題はない。むしろそんくらいしてやんねぇと、いじけてぐすられるほうが面倒だ。面倒なんだよぉ、オレは勝手に惨めんなって、笑ってやれなくなるから。いじけたって泣きはしねぇけど、オレがいつも通りじゃなきゃ不安がって、そのうちに泣きだしちまう。いっぱいに涙を溜めて、ぐじゅ、と泣くから。声も出さねぇで哀れっぽく、オレはどうにも極悪人みたいな気分になって、泣き止むまでどこにも行けやしなくなる。
俯いた滿月の髪がたる、と滑って、暗がりの顔を液晶が照らしてる。目ぇ悪くなんぞ。唸りながらじっと文面を読みつくして、ぱっと顔を上げた。見開かずとも大きな瞳と目が合う。
「この子は下心があるわよう、絶対に、メールだけじゃございませんでしょうに、隠し事をなさるの? 物事の本質を、ご理解できぬ頭だったかしら」
「ハァ、オマエは」
「ひどいひと、荒巻、あなたがわたくしにオマエだなんて、そう、そうなの。粗雑な呼びかけをなさってよろしいと思っておりますのね? 随分だわ!」
やっぱり仔犬だ。毛の長い、自分の毛にもつれて転ぶような犬。きゅんきゅん鼻鳴らしてやがる。ああだこうだと口うるさく、無駄に言葉を重ねて、少しでも気に入らないとすぐに顔を背ける。いやに神経質で、でもどこか抜けてて、見てなきゃなんねぇちまっこい生き物。
「みつき。ンで、確かに馴れ馴れしく話しかけて来やがったけどよぉ、いつも通りだ」
「また怒鳴ったのね、女の子に手酷い扱いを」
これだ、滿月はぷいっと鼻っ面を他所に向けて、長い髪が揺れる。下唇をキュッと持ち上げて、なんとも言えず拗ねた横顔である。なんだその顔はと苦笑いすれば案の定、今度は頬をふくらませてくる。アーもう、面倒くせぇの。なんだってオレはこんな女のご機嫌取りなんぞするかね。こいつがオレの機嫌取ったことなんざねぇってのに。
「オマエ、ン゙ン゙、みつきの言う手酷い扱いじゃなきゃ、またきゃんきゃんウルセェだろ。どうしろってんだよぉ」
「人間の配慮と誠意の範疇で関わってくださいまし、いきなり怒鳴るなんて、人間性の欠如が著しいわよう、いまだって、わたくしを犬のように。まあこの世の獣は全てわたくしより愛らしく尊いけれども」
「犬みてぇってのはそっちがきゃんきゃん吠えるからだろうが」
「またそんなことを……あなたはほんとうにどうしようもございませんこと」
ぢと、と鈍間な視線で刺してくる。オレが悪ぅございやす、ハイハイ。まんまる頭の気取った髪をかき混ぜればにまっとした。不服さと心地よさの間のわらいだ。
「テメェは鬱陶しいんだよぉ」
「おれ喋ってないじゃん!」
「動きと存在が鬱陶しいっつってんの」
「存在“感”とかじゃねーんだ、おれなんだ……おれだって犬系だと評判ですけどねッ」
「言ってて恥とかねぇ感じ?」
「穴掘って埋まりたい感じ」
指差して笑っといた。サッサと掘れよぉ、墓穴ってやつを。墓石に上等に彫って残しといてやるさ、バカここに眠るってな。目覚めたら過去にタイムスリップ、一昨日あたりじゃねぇか? さて、機嫌治ったかと滿月を見れば小難しい顔してやがった。ろくなことになんねぇだろうな。
「まったく、犬に失礼だわ。人間なんて碌なものじゃございませんに」
滿月はしれっとした顔で続ける。かこん、こくん、頭を揺らして、少しも悪びれない。長いまつ毛の陰に黒い瞳が潜んでいる、やけに艶やかだ。手のかかる女。こっちがいちいちツッコむのも面倒だってのに、どうしてこうも言葉が止まらないのか。そんな揺らしちゃことり、と落ちちまう。耳を塞ぐように両手で支えた。そういや、血潮の音は地面の深いとこの音に似てるらしい。溶岩だったらいいな。この手のひらから幾ばかりの熱が奪われても、なお焼けるほどぐらぐらと煮えてりゃいい。
「ホント動物好きだよな」
「動物だけじゃないわよう、人間以外はみんな、人間より素敵だわ。すてきないきものの血肉で生きている、あ、バッドはいる」
「おいまて、哲学でバッド入るのやめろ、病むな」
掴んで引いた手首は恐ろしく細かった。骨の軽い硬さが手のひらに残る。無臭の、空気だけが流れていった。抱きしめたって冷たい、冷たいのが悪いよな、オマエはもっとやらかいだろ。
「荒巻くん、抱きしめてよろしいとは言ってないわよう」
「じゃ、いま言え」
「よろしいわ、存分に! ぎゅーーーーーってしてくださいましね、締め落としてちょうだいな。罷り間違って死ぬまでいったら餞にちゅーしてくださいまし」
視界の端で北原は後退っていく。離れんのはいいけど無言で引くのはやめろ、手で顔を覆うな、指の隙間から見るな!
オレだって好きでこうなってんじゃねぇってのに。
「……ふふ、やっぱり荒巻くんは素敵だわ。ああ、こうして永遠にぎゅーってされていたい……あっ、でも永遠はちょっと長いかしら。百年くらいで」
「百年も長ぇよぉ。つか、どんだけぎゅーってされてぇんだオマエは」
「わたくしはぎゅーってされるために生きてるもの! ああ、どうぞ、そのまま……」
こいつはほんと、どうしようもねぇくらい手がかかる女だ。与えりゃ喜ぶクセに、ちっとも欲しがりゃしねぇのも。欲しいもん以外は要らねぇのも。耳元でため息ひとつ、ほら、オマエのせいだぞ、惨めんなった。
「ため息ばかり、付き合ってもいない柔の女を自ら抱えて、どうしてそう、恰も面倒を見させられているという態度をとるのよう」
「……付き合ってないって言ったか? 荒巻? 嘘だよな?! こわいッ!」
バダバダと溺れてもがくような足取りで逃げてった背中に中指立てて、また滿月をきつく抱きしめた。オレだってこわい、怖くって寝れやしねぇくらい。この距離が、幼く馴染んでしまったから。冷えた女を置いてやいけねぇから、オレの血潮は溶岩じゃなくて、心臓は幾ばかりの熱を巡らせるばかりだから。離れちゃ、滿月はやらかくなんねぇから。
「オマエが振ったんだろぉが」
「だぁって、恋じゃございませんもの。すきよ、だいすき! 恋する乙女ってすてき、それは初恋ならなおのこと、いつかね、わたくしもそうなりたいの。オマエなんて呼ばれても、だいすきなのよう、これが恋になるのやも」
きゃらきゃらわらって、胸元に擦り寄ってくる。滑る髪が女の形を曖昧にする。どこからどこまでが冷たいのか、確かめることを許されていない。
「荒巻くん、だいすきよ、結婚したって幸せ。わたくしね、あなたの幸福になれるわよう。でもだめね、恋してないの、いつか初恋もらってくださいましね」
「はやく、全部寄越せよぉ」
「いつになるかしら? いつ、誰かしら。荒巻くんだったら、うれしいとおもうの」
光を逃さない瞳。つるりと輝くのにいつだって真っ暗だ。いつのまにか外は清々しく静まり返って、木の葉の一枚だって揺れることはなかった。
「燃えるような初恋の果てに、灰燼のわたくしを融かして宝石にしてくれる、一等の誰か。煌めくわたくしを見て、どこかの乙女がまた恋するの、初恋ってなんて素敵なのかしら! って。初恋に恋するのよう」
詩を謳うみたいに流暢で。どろどろ熱い、赤熱したガラスの如き声だ。きん、と響いて突き刺さる。呆気なく砕けるくせに、皮膚を裂いて肉に食い込んで、ずっと痛い。オレは冷たいから、オレの熱はこれっぽっちも足りないから、融かすどころか燃やすことだってできなくて。いまだって、こんなに近くにいるのに。
初恋とやらに恋しちまって、だから初恋なんざとっくにねぇくせによぉ。どうやってもらってやったらいい? オマエが身勝手に遠くにやっちまったもんを、オレはもう何年もずっと、捜しまわってるってのに。オマエが足にじゃれつく仔犬のまんま、うつやかな女の顔して凭れるまんま、冷えて形の保ったまんま、ちっとも動きゃしねぇからよぉ。抱えて行こうにもオマエは、あれが気になるこれを見てたいだの、我儘ばっかりで! あんまり遠くにやっちまったくせに、もうどっちにやったかだって憶えちゃないくせに。
「ホント、かわいい女だよぉ、みつき」