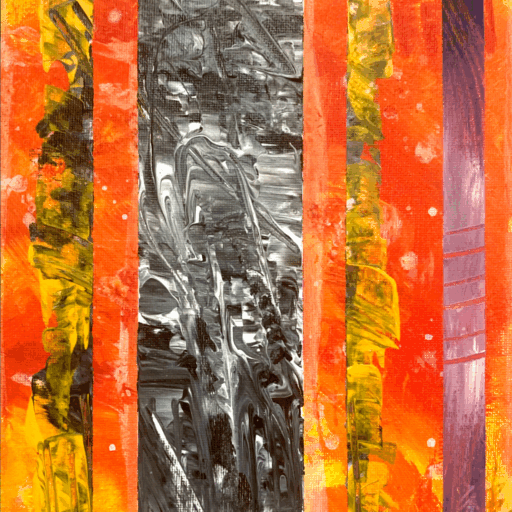「オマエの歌はまるでラトルね」
いつだって一番奥に座っている。気がつけば扉からすぐの椅子に腰掛けて、何をするでもなく、ぼぅ、と視線を寄越している。ともすれば微睡んでいるようにも見えるその様を、この教会以外で認めたことがない。
「騒音だって言いたいの」
「あんな歌をうたうくせ、情緒的でない人」
歌うように、嘯くように、囁く姿は美しくて、目障りだった。蠱惑的で、退廃的な、鏡台のよく似合う女。赤みを孕んだ豊かなブロンドを手櫛で梳くのが癖であった。蜂蜜を流し込んだような透き通る瞳は貪欲に光を捕らえている。一挙手一投足に視線が纏わりつくのが常である、言うなれば、ファム・ファタール。
「そういうあなたは味気ない人よ」
「マ、ひどい。皆がみなワタクシをスウィーティと呼ぶわ、スウィーティ・ストロベリー! ワタクシがご存知ないとでも思ってらして? ネ、ダーリン」
「やめなよ」
口をついて出たのは、呼称にか、それとも身の振り方にだろうか。気に食わないと素直に思った。薫るフレーバーに誤魔化された、無味乾燥の女。肺を犯すマネをして、身になることなど一度もない。その生き方を愉しんでいるようにも見えないのだから難儀なものだ。
「どうして」
「そんな仲じゃないでしょ」
「相変わらず一途ね、オマエ」
一途など、解せない言い回しをする。俗物的な文脈に当て嵌められるなど、私の信仰心への侮辱に他ならないというのに。半端にひらいたぶ厚い唇が息を吐く。熱の行方を辿れそうなほどの、深くから引きあげた息を。私の肺にも、希釈されたフレーバーが染み付いていく。
いつも対話の終わりは明確で、だらしなく座面に身を倒した女がすっかり隠れてしまったら。こうなった女は二度と口を開かないし、私がなにかを問いかけることもない。女がいつのまにか出ていっても私は歌い続ける。ステンドグラスを塗りつぶす赤い光が髪を焦がして、冷え切った風が鋭い爪の先で肌をなぞっても。
ふるりと身震いして気がつく。月明かりさえない純な暗闇があらゆる正確さを覆い隠していた。瞼の裏は依然として眩く網膜を焼いている。光ばかりを見つめながら足音の響きを頼りに曖昧さを掻き分けた。慎ましく穏やかな呼吸は信頼の証。我が父の家に恐るべきものなど何もないのだ。
「ぎ、ぎゃあ、はっ、ひぃ……は、ぎぃ、がひゅ」
歯を食いしばって、悲鳴を舌ごと飲み下そうとして失敗したような、隠さなければならなかったものが堰を切ってしまったような、あってはならないこと。ともかくそういう風だった。鼓膜にじっとりと張りいて剥がれない呻きは次第に激しくなる。そのうちに息の吐き方を忘れてしまったのか、惨めったらしい声色でしゃくりあげていた。
「ひぎゅ、ひ、ひ、ッぎ、ひゃ」
隣に座った。女は寝転がっているから、身じろぎ一つで髪に触れるほど近かった。女は苦しんでいた。それさえあれば十分だった。息を吸った。深くまで引き込むように。前を見ていた。痛むほど燦々と輝く、きっとこれが。暗闇を押し除けるように、ほんの少しのゆとりもありはしないように、この場に愛だけが満ちるように。
ラトルって、想像よりずっと素敵な役回りかもしれない。
まともな呼吸が二人分。幾日ぶりにも感じられる静寂に身を委ねていると、ぱっちりと見開いた女が私の手を握った。手の甲を引っ掻かれて、整えられた指先が存外に丸いのだと知る。傷つけられるしかないのだと叫んでいる気がした。
「酷いゆめを」
「そう」
「失恋したの、ネ、なんにも言わないでいて。ぱちぱちしてたわ、瞳の内側から……いままさに火をつけようとするみたいに。燃え上がる瞬間を見逃しちゃった。光よりも温度を感じたのよ。ワタクシの涙じゃ足りなかったの、あんまりに熱いから蒸発したんだわ」
「なんにせよ、泣き止んだならよかった」
「よかったの? あはは! はは、ふふふ。まるで、泣いてたら困ってくださるみたい」
無口な女、回っているだけの舌に意味はなく、不自然なほど光を湛えた瞳ばかりが意思の在処だった。夜は短い。女の視線をありったけ受け取るには、夜はあまりに短すぎる。
手の下に女の指先が潜り込む。磨かれた爪の感触が掌に残った。女は目を合わせながら視線を彷徨わせている。右目を見て、左目を見て、戸惑っている。想像だにしない現実を認めたくない時のように、女はまっすぐと粗を探していた。窓を、閉めてやらないといけなかった。私がしてやれることはそれくらいの小さなことだった。連れて行かれると思って、女“に”か、女“が”か、定かではないけれど、ともあれやらねばならないことだった。さっさと女の手を離して、立ち上がってしまわなくては、手遅れになると確信していた。歌声すらも届かぬ遠くで、また魘されて、ひしゃげた喉で喘ぐ夜を過ごすのだと。けれど私はどうして、熱い手を握ることしかせずにいた。女が不審の表明として笑うたびに、柔らかな髪でささやかに擽られる肌が引き攣った。熱も、言葉も、真実も、受け取って、返すものがなくて、絡めた視線を誠意とした。夜は短い。女の口角が持ち上がる。仕様のないことの、仕様のないままの終わり方を知っている顔をして、それが笑顔のふりをする。私の手の内にあるのは冷え切った空気だった。女は起き上がって、乱れた髪を手櫛で梳いて、笑った。
「なにをしてらっしゃるの?」
なんにも言わないでいた。温度と鼓動と呼吸以外の全てが無意味だ。窓を閉めてやらなかったから、寒くて仕様がない。私よりも、背が高い。科を作って首に回された腕が、女の甘さを示しているようだった。女“と”かもしれないって、どうして、考えちゃいなかった。
私は女の名前も知らない。ああ、この女に、呼べる名前はあるのだろうか?
胸中には甘い薫りが満ちていた。薔薇と蜜蝋を暖炉に投げ入れたみたいに、炎がごうごうと燃えているのだと思った。合成香料や人工甘味料なんかとは程遠い、自然のものでつくられた女。色とりどりの光に眩んで瞬きをした。瞼の裏に、闇に底光りするあの瞳が、それかいつも通り、全てが閃々と真っ白だった。女が泣いてなんていないこと、今更に悟ってなんになる。気まぐれな女は気がつけばいなかった。ちりぢりに拡散した朝日が女の痕跡を塗りつぶしているようで、あくびが出た。目を瞑らずに眠れたら、悪い夢は見ないだろう。