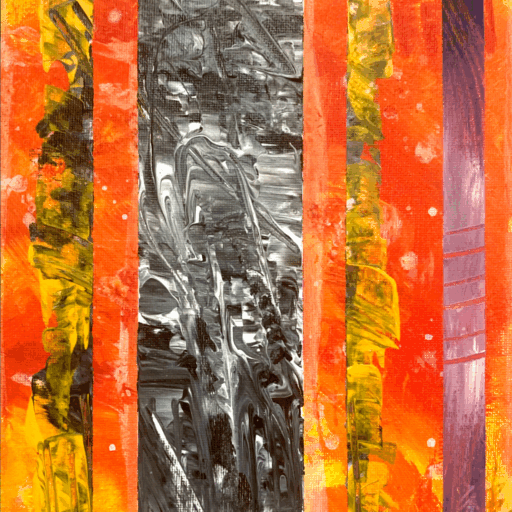器量の良い女がさめざめと泣いていた。暗い森をうつしたような深緑色のベルベットのワンピースは裾が破れてはしたないスリットが入っている。眩いビジューで飾られたハイヒールのパンプスは傷だらけで、左足のヒールは折れていた。絹糸を油煙墨に浸したような長い髪だけが妙に綺麗だった。
「あ、あぁ、どして、わたくしなの、ひどいことばかり、わたくしなのよう」
白魚のような両の手で、まあるい両の頬を包んで、ぼろぼろと涙を溢す。伏した睫毛の震える様といったら、身慄いして生唾を飲み込むほどに艶やかだった。美術館から飛び出してきたかのような美しいもの。額縁を越えて触れられる距離にいるならば、後先考えずに攫ってしまいたくなるようなとびきりの美人だった。そんな絶世の美女が、薄暗い路地裏の埃まみれの室外機の隣、捨て置かれた観葉植物の前でひとりぽっちで泣いている。走り抜けるねずみもワンピースを這う虫も無視して呪詛を吐きながら、きったねぇ壁にもたれて打ちひしがれているのだ。
「なあ、なんで泣いてンの」
頭上から声を掛けられても女は嗚咽を洩らすばかり。いつからか側に人が立っていたのは気付いていたが、そんな些細なことよりも胸に巣食う絶望を吐き出すことで精一杯だったのだ。女はぼんやりと、おとこの人だったのね、なんて思ってお仕舞いにした。
「なあ、聞こえてンだろ、美人の女」
また一匹、ねずみが通った。男の靴に登った虫は振り落とされて踏み潰された。それから男は女のワンピースを我が物顔で這い回る虫を摘んでとって、やっぱり踏み潰した。女は気にも止めずに己が不幸を反芻しては新鮮な憤怒を燃え上がらせていた。
ぞんざいに扱われていることを良しとしたことはなかった。けれども女を丁重に扱うのは本人たる女ばかりで、金も権力も武力もない美しいという事実以外になにもないちっぽけな女には抗う術などなかったのだ。だから奪われた。いっとう大切なものを。代え難く、人間であるかぎり須く守られるべきものを。なくしちゃったから、なくしかないのよ。
「なあ、女、おまえだよ、電球みてえな女」
「無礼なおと、こ」
ひゅっと息を飲んだ。悲鳴をあげようとする喉を締め付けたのは女の最後の矜持からだった。堰き止められた空気が暴れてかえるのような音が鳴ったけど、それで済ませた自分を褒めるべきだ。
虫を摘んでいた手がこちらに向かって来たことは気にも留めていなかった。今更だ、頬を張られようとどうでもよかった。その手が髪に触れようとしなければ、女はひとりで泣いているだけだった。叩き落とした手を追って顔を上げた先には、逃げ出したくなるような醜男がじぃ、と女を見つめていた。表の通りに出れば子供は泣き叫び大人は吐き気を堪えて逃げ出すような、かえるのような見て呉れの男。涙で歪んだ視界でも紛れぬ醜さは、童話に出てくる呪われた王様の成れの果てのようで、いっそ哀れなほどだった。そんな目も当てられぬ醜形の男が、彫刻もかくやという美女を見下ろしている。第三者がこの現場を発見すれば迷わず国家権力に通報するような絵面だが、こんな衛生環境が底辺の道をわざわざ通るような物好きは女と男以外にいないだろう。ふたりきりの路地裏で、男と女は出会ってしまった。
「ぴかぴかしてンなあ、おまえ」
「しってるわ、わたくしだもの」
男のぼこぼこした顔面に浮かぶ嫌に大きい瞳に怯えながら、震える声で答えた女はもう泣いていなかった。やっと返ってきた関心に気を良くしたのか、男は荒れた唇を引き伸ばし笑みをつくった。裂けた皮膚から滲む血が生々しく赤くて、女は目の前のかえる擬きがちゃんと生きていることを思い知ったのだ。現実を捨てようとしたイカれた脳内産の化け物では無かったことに安堵し、そして落胆した。もしかしたらこんな醜男は存在しないのかもしれないという一抹の希望が消えた瞬間だった。
「なんで泣いてたの」
「なくしちゃったの」
「なにを?」
「尊厳」
面食らった顔をして、大きい瞳をさらに大きく見開いた男は、ゆっくりと息を吸ってから大笑いした。
「ひはははは! はっ、んはは、げほっ、おまえ、っぎゅ、ははははは!」
時々咽せてはかえるのような音を出す男を見て、笑いなれてないのね、とか思った女はそっと耳を塞いだ。狭い路地裏に無遠慮な大声が反響して耳が痛い。自分の啜り泣く声ばかりを聴いていた女にとって突然の爆音は辛かった。女が整った顔をしわくちゃにしながら堪えること数分、息も絶え絶えになった男が泣きながら地面に崩れて静かになった。今度は女が見下ろすことになって、先ほどよりも顔の細部がわかるようになった。目の色が極端に薄くって、昔お家にいたおじいちゃんの犬を思い出した。おっきい犬、ワイマラナーとかいう灰色の、女が産まれる頃にはもう白内障だった穏やかな犬。その目で見たなら、わたくしはさぞぴかぴかでしょう、と内心で頷いていた。
「あなた、お名前はあるの」
「あるよお、かわづふゆ」
「なんて書くの」
「風に祐けるで、風祐。おまえは? お名前あるンだろ」
「いはる、怡びに、陽なたで怡陽」
ちゃんと漢字も説明してやったら、男は口を真横に結んで、それからもにもに動かして黙っていた。それにしても、かわづだなんて。麻布のような燻んだ白の虹彩に書き損じみたいな瞳孔の不気味な瞳が、女の髪を一本ずつ辿るように見ていた。女は乱れた髪を手櫛で纏めて弄ぶ。珠の肌を覆うこの眩く煌めく髪が、女にとって服よりも信頼のおける装甲だった。光とともに不躾な視線も悪意も撥ね除ける女の自尊心の体現。容易く触れさせるわけがないのだ。
「いはるちゃん、俺よろこびって漢字わかンない」
「じゃ、陽ちゃんって呼びなさいな」
「そおする。俺はゆーちゃん?」
「わたくしは両方の漢字がわかるから、風祐くんよう」
「風祐くんが取り戻してやろおか」
「なにを?」
「尊厳」
女は切れ長の眼を彩る長い睫毛を揺らしぱちぱち瞬きして、砂利のように粗い響きを持つ声で伝えられた言葉をよくよく噛み砕いて、くふくふと喉の奥で笑った。男はなんてことない顔して女の顔を覗き込んでいる。一向に見慣れない醜さの男は、地面に寝転がったものだから汚れてさらに嫌悪感を煽る見た目をしていた。女は土埃に塗れた髪を耳にかけてやって、耳と歯の形は整ってるのね、なんて思ったらもうだめだった。父が見ればすぐさま怒鳴りつけるであろう、大口を開けた淑女にあるまじき笑い方をして、涙を一粒ころがした。
「取り戻してくださるの、ふふ、わたくしの尊厳、あははっ、すてきね、ふゆくん、すてきなひとだわ」
きゃらきゃらご機嫌に笑う女はきっと世界で一番可愛くて、男はそのまろい頬に掌を差し出した。さらさらと流れる細い髪には触れぬように気を遣いながら。男の樹皮のような肌では傷ついてしまうだろう。息を落ち着かせようとした女は、目の前の男が自分を尊重したことを認めてまた腹の底から声を出して笑った。男は耳を塞がなかった。ガラス細工の如き繊細さを孕んだ声がふたりを包んでいる。男の手首を引っ掴んだ女は、そのまま頬を擦り付けてやった。ひっかかる肌がぴりぴりと痛んだが知ったこっちゃなかった。
「はるちゃんの尊厳を奪ったやつ、どこにいるの」
「表の通りの一番大きなホテルの、一番上。それから、わたくしのお家」
「家にもいンの」
「父と祖母と姉がいるの」
「俺がさ、取り戻したら、ご褒美ある?」
「宝石なら、あげられるわ。装飾品なら与えられてきたもの」
「ンー、いらない」
「じゃ、なにがいいの」
男は視線をうろうろと彷徨わせて、女に捕まった手を引っ込めた。口元を覆って暫く固まって、いそいそと起き上がって姿勢を正す。正座した膝の上に乗せられた手が白くなるほど握り締められていて、女はその手を取って撫でてやりたくなった。お互いが黙ったまま、お互いのことばかり気にしていた。やっと腹を決めた男はごきゅ、と唾を飲み込んで口を開く。
「俺と、一緒にいて。手ずから飯食わせてくれて、ベッドの隅っこに置いてくれたら、いいよお」
「わたくしを、まるごと欲しいのね」
「くれる?」
女は蛾眉をなだらかに、眦をさげて、頬をゆるませた。つまりは目も眩むほどの笑みを湛えて言い放った。
「あげる!」
弾む声をしかと聴いた男はすぐさま飛び上がって表の通りに駆け出した。一番大きなホテルの一番上を目指して。女はその背中に「待ってるわ」なんて言葉を投げてやった。男が何をするつもりなのかは知らないが、何もできないだろうということは女がよく知っている。ボサボサの髪に埃まみれの服を着た汚らしい醜男に、金も権力もないであろう誠実なだけの男にできることなどない。それでも、そんな現実を理解していても、女は夢見がちなところがあるから。本気で言ったのだ。まるごと全部をあげる。叶うはずがないけれど、尊厳を取り戻してくれるって本気で言うものだから。誠意には誠意を、それが女の生き方だった。
太陽がひと足さきにと逃げ出して、光を独り占めした月が顔を出す。男を見送ってから一時間ほど経っただろうか、女は未だ路地裏に座り込んでいた。放り投げた鞄から何度か着信音が聞こえたが全部無視して男を待っていた。連絡もせずこんな時間まで外にいるなんて初めてで、父も祖母も姉も不機嫌だろうが気にしちゃいなかった。だってもう女はあの家のものではないのだ。男が全部貰い受けてくれる。浮かれた女は気づかなかった。度を超えた傲慢が、己の所有物が歯向かうことを許すはずがないのに。
「おい、帰るぞぐず女」
声は出なかった。唖然と見上げる女は前髪を自分勝手に引っ掴まれて無理矢理に立たされる。よすがの髪がぶちぶちと千切れ抜かれていく痛みだけが確かだった。嗄れた声に温度はなく、歪んで痙攣している口角や目元が内で暴れる激情を表していた。こういう人だった、ずっとそうだ。平静と体裁を保とうとするくせ、癇癪を抑えきれない馬鹿。女はもうおかしくて仕方なかった。醜い人。世界一の醜男に出会ったばかりだ思っていたのに、もっとみっともない人がこんなに身近にいたなんて!
「うふふ、ふふ! とうさん、わたくしの父、ふっ、あはは!」
「説教は、後にしてやる。帰るぞ。みんな、心配していた」
怒りで息を荒げて、それでも外面だけは崩したくなくて、不自然な間を作りながら話す父についには大声で笑ってしまった。父は初めて見る明け透けな女の様子に狂人を見るような目を向けて、掴んだ前髪をそのままに引き摺って車まで歩く。女は痛みを無視して必死に振り返ろうとしていた。そっちじゃないの、ちがうのよう、あっちにいかなきゃなんないの。けらけら笑いながら女は背後に手を伸ばす。がさがさの、女を傷つけるあの手に助けて欲しくて。一歩、一歩、ヒールの折れた左足を言い訳にしてのろまに歩いたけれど、ドアが開く音がして、父が立ち止まって、投げ込まれることを覚悟した。
「待って、待ってよ。俺も連れてって」
「取り込み中だ、見てわかるだろう。なんだ、その醜い面は、お前のような見窄らしい人間が声を掛けていい相手ではない」
「なあ、はるちゃん」
「わたくしの父よ」
「わかったあ」
がつ、と鈍い音がして痛みが消えた。くちゃくちゃの前髪の奥で顔面から血を流した父が地面に這いつくばっている。ドアを開けていた運転手が駆け寄っていくのを男の腕の内側から見ていた。女は笑いすぎてお腹が痛くって、やっぱり涙を一粒ころがした。携帯電話を取り出す運転手にワインボトルを躊躇いなく投げつけた男は得意げな顔で囁いた。
「あと、二人だけだなあ?」
「きっとよう、楽しみだわ」
「おい、おい! 馬鹿女! けっ、警察だ、早くしろ!」
「どうして」
「はあ? 父親が殴られたんだぞ、そ、そこの蛙の化け物に! そうだ、人攫いだ、お前を攫いにきた、通報しろ!」
「ちがうわ、わたくしのお友達よう! そんなに言うなら、ご自分でなさったらいかが」
「はるちゃんは俺とお喋りしてンだろ、死ねようるせえな」
「ぷぎっ」
米神をぶん殴られて気絶した父を一瞥して、豚だったのね気づかなかったわ、と思ってお仕舞いにした女はパンプスを脱ぎ捨てた。金も権力もないけれど、女と違って武力があった男の首にうんと背伸びをして手を回して甘えてやる。
「足が痛いの、運んでちょうだいな」
「いいよお、俺が運んであげンね」
もう聴き馴染んだ鼻濁音が際立つ口調と見慣れた容姿。壁に投げつける気もないし、男には帰りを待つ従者なんていないだろうし、この見て呉れは呪いなんかじゃないって知ってる。女はこれでいて現実主義なところがあるから、真実の愛も王様もここにはないって理解している。けれど女はぐっと近くなったでこぼこだらけの顔をじっくり見つめて、頬と頬を擦りあわせて、瘡蓋のできている唇にあいらしく口付けしてやったのだ。
「なっ、え、はるちゃ、なんでえ!?」
「あははは、ふふふ、んふ、ははは」
相変わらず男は醜くて、女はなによりも美しい。「ばあちゃんとねえちゃんがまだ」だとか、「肌が傷ついちゃう」だとか、瑣末事ばかりの口をもう一度塞いでから胸に耳をくっつける。人間の鼓動の音がして、鼻を明かしてやった気分になった。蛙の化け物なんかじゃないわ、すてきなわたくしの風祐くん。
「ねえ、風祐くん」
「なあに、はるちゃん」
「幸せンなろぉね?」
「ひはは、可愛いなあはるちゃん。幸せンなろおな」
不法侵入も殺人未遂も須く無視するべきだ。だってふたりはこんなに幸せ。ご機嫌にはしゃぐ女をあやす軽い足取りで夜の街を行く男はかえるのようで、けれどとびきりすてきな男だった。