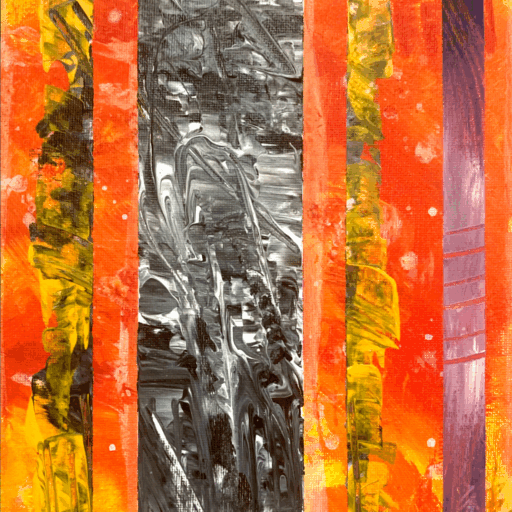祭壇を飾る美しい花々を、一輪づつ摘み取る。萎れてすらいない首を折る。指先が緑に濡れてべたつく。青臭い匂いがした。咲き誇る花に翳りを、私の手に傷はない。棘の削がれたものばかり。放った先は花籠か、屑籠か。冠の作り方を教えてくれる人はいなかった。
「お手伝いしてさしあげる」
「どうして、ここにいるの」
「ワタクシに帰るところがあると思って?」
女の薄い爪が花弁を引っ掻く。はらと舞ったそれは、私の足をそっと撫でて地に落ちた。
「ある。絶対に、どこにだって」
「ここは、ワタクシの家じゃないわ。学校の小さな礼拝堂も、一番通りのここよりずっと大きな教会も、ぜんぶ父のための。知ってるでしょう」
そんなことを言いたいわけじゃなかった。どこだとか、なにだとか、明確で物質的な答えに意味がないことくらいわかってる。ただ、どこにでもあって、それはいつ何時であっても絶対で、この華奢な女は守られていなければならないと。なんて言えばよかったの。手折られた花を引っ提げただけの私が。
「これでも被ってなさいな」
頭に軽やかな質量。青々と、そして咽せ返るほど濃い花の匂い。女の指は白いままだった。籠を奪った女が笑う。私の汚れた手をとって、拙いステップでリードする。花の無い祭壇、火の灯らない燭台、揃わない足音が反響して耳が痛かった。歌う余裕もないくらい不恰好な大人の真似事。女は笑顔で私を見下ろしている。ぐらり傾いていく視界の端に、我が父の血で染めたようなサテンの艶が。縺れた足に焦りもせず女の手を離した。お気に入りの深紫のワンピース、私ね、笑えるほど似合わないのよ。
「目を瞑ったからだわ」
立ち上がって、スカートの皺を伸ばす。よく似合うけれど、汚れていたら台無しだ。白なら尚のこと、しゃんとしなければ。私も、帰るべきなのだろう。朝帰りした娘に両親はなんと言うものなのか、皆目見当もつかない。なんにせよ、私の家はここじゃないから、帰らなきゃ。
一歩外に出れば、朗らかな陽光に花壇の朝露が輝いていた。二十分も歩けば着いてしまう。ちょうど一度目の朝食が始まる頃だ。きっと母はいつものシリアルを戸棚に仕舞い込んで、プレッツェルといくつかのチーズにサラミとゆで卵を用意しているだろう。父は髪をワックスで撫で付けて、執拗に磨いた革靴を穿いて新聞を取りにいくだろう。数日のうちに家中が整えられ、野晒しのポストでさえ塗り直された。全ては兄のために。
「おはよう、母さん」
「おはよう、エリー。朝食の準備は済んでるから、アンディを起こしてきて」
頬を張られるのは慣れた。直後に微笑まれることも。長々と叱られるよりよっぽどありがたいけれど、兄には一度もやったことがないって知ってる。いつまでも兄が大好きね、仲が良いのは素敵なことだわ。豪華な朝食も、お土産のスノードームも、不意に投げられる小言も、ええ喜んで。親兄弟を愛するのは当然だもの。
「エリー、今日は暇なんだろ。服でも買いに行こうか」
「いいえ兄さん、教会に行くの」
「典礼も聖歌隊の練習もないのに?」
「我が父に会いにいくために、もっともらしい理由が必要?」
「主は家族を大切に、と言っているよ」
「だから、ここにいるのよ」
席を立てばもうなにも言ってきやしなかった。自覚がないのも考えものだ。賑わうダイニングに背を向けて足早に階段を上る。自室の扉の前に兄の荷物が置かれていた。雑多な人、構やしないわ。見慣れた部屋が妙に懐かしくて嫌になった。昨日カーテンに振った香水の残り香が、どうしてか鼻につく。朝帰りの甲斐あってベッドメイキングの手間が省けたから、軽くシャワーを浴びて身なりを整える。一番濃い色のワンピースを手にとって、やめにした。やっぱり似合わないから。鏡の中の私は笑っていなかった。部屋を出ると端に寄せた荷物はなくなっていて、一階から談笑する家族の声が響いている。静かに家を出た。そういえば、お土産をテーブルの縁に置いたまま。スノードームは嫌いだって、何度も言ったのに。
朝食は一度で十分、シリアルだって素敵。それよりも夕食には温かい料理が食べたい。舌に残るからいヴルストよりも自分で作るローストビーフが好き。週末のお出かけが遊園地になったのはいつからか、家族が典礼に参加して祈りを捧げている姿を想像もできなくなったのはどうしてだっけ。私にはまだ、家族がいるのかしら。太陽が眩しい。くっきりと、影が残る。