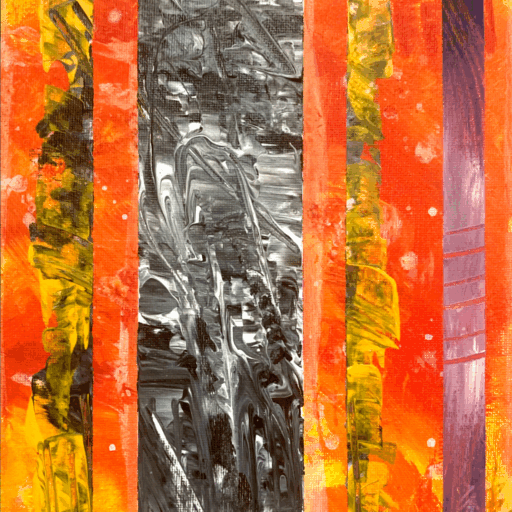ピュートは孤児だ。気がついたらスラム街で生きていた。得意なことは死体漁りと物乞い、苦手なことは死体との同衾。詐欺やスリや暴力からは距離をおいて(自主的には行わないように)生きてきた。もちろん稼ぎは劣るし、短絡的で粗暴に解決する方法を羨んだこともある。けれどピュートは死にたくなかった。こんな産廃と気狂いの掃溜めで生きるのはいやだったし、不幸だともおもったが、こんなところで死ぬ不幸にくらべたらなんてことないのだ。いつ死ぬともわからない人生でそんなリスクは犯せない。ピュートは幼いころにラリった歯抜けジジイに耳が聞こえなくなるまで殴られてから、少しばかり頭が足りなくなったが、足りないぶん時間をかけて考えるようにしていた。そのおかげで自分がまだ死なずに済んでることをよく知っている。ふつう、片耳が聞こえなくて、頭が足りなくて、脇腹からもう一本腕が生えているような人間は、両手の指ほども生きられない。それがスラム街ならなおさらだ。ピュートが少なくとも両手の指以上に生きてこれたのは偏に自分を過信しなかったから。恥晒しと詰られようと、臆病者と嘲笑されようと、ピュートは決してこの街を出なかったし、自分から暴力に訴えることもしなかった。いま自分をばかにしている奴らは、近いうちに死ぬ。実際、逃げ足を自慢していた男も、色仕掛けに自信があった女も、一ヶ月もすれば路地裏に捨てられていた。やっぱりなと呆れみながら死体を漁って、いくつか売れるものを頂いたら肉は回収場に持っていく。
ここらには回収所と呼ばれるものが点々とあって、大抵は袋小路になっている。そこに死体を持っていくと、鮮度やら容姿やらで価値がついてちょっとした小金稼ぎになるのだ。買取人はコロコロ変わるけど、査定の仕方は変わらない。きっと決まりごとがあるんだろう、ありがたい話だ。二ヶ月前までやってたおじさんは世間話もしてくれて気に入っていたけど、いつの間にかいなくなってしまった。スラム街では他人との交流が必要不可欠だ、良い意味でも、悪い意味でも。どこそこのギャングが内輪揉めしてるだとか、最近はやりのドラッグは数回やっただけで戻ってこれなくなるとか、身を守るためにはできるだけたくさんの情報を集めなくちゃならない。そしてそれは何かを攻撃するときもいっしょだ。おじさんはたぶん、喋りすぎちゃったんだろう。どっかの肉屋にでも並んでるんじゃないかなぁ。
これもそのおじさんが教えてくれたことで、回収場に持ち込まれた死体は大まかに三つに分けられる。鮮度がいいのが臓器売買、容姿が整ってるのが美術品、どっちも悪いのが加工肉。臓器売買は医者とか薬屋が、美術品はそういうコレクターがいるらしい。お金持ちの趣味はわかんないけど、好みの人間を剥製にするんだって言っていた。そんでのこりが加工肉になる。ここじゃ肉は嗜好品で、ふつうの肉(牛とか豚とか)はとびきり高価だった。だから簡単に手に入るものを食うのだ。ちょっと手間がかかるけど、煮込んじゃえば臭いも筋も気にならないって。ピュートは昔、ほんとうになんにも食べるものがなくなったときに下の腕(右の脇腹に生えているのをそう呼んでいる)をちょっと食べたことがあるけど、焼いただけだったのが悪かったのか惨めったらしいほど不味かったから、人の肉は二度と口にしないと決めている。それにピュートは馬の肉がすきだった。スラム街と人間街のギリギリで死んでるのをがんばって引っ込めたやつを食べたことがある。毛皮とか馬装具が目的だったけど、腐ってなかったから肉もちょうだいしたのだ。無茶させられた老齢の馬は固かったし、血が回って獣の匂いがしたけど、自分の腕を食べたあとだったからずっと美味しく感じた。それ以来ピュートは馬がすきになった。肉や毛皮だけじゃなくて、顔つきや動き方も。いつか乗ってみたいと夢をみている。もっとも、生きた馬がスラム街にくるなんて、誰かが捕まるときか殺されるときくらいだから、叶うはずないけど。
この街はときおり皆んな仲良くなる。足つきが逃げてきたときとか、お忍びが観光にきたときとか、全体がまんべんなく不利益を被るときは、さっきまで殺し合ってた奴らも肩を組んで歌い合う。衛兵が踏み込んでくるときは仲良くしなくちゃならない。うるさくすると気まぐれに殺されるし、女だったらもっとひどい目にあう。でも足つきはとっ捕まえて突き出せば報奨金がもらえるし、気に食わない奴を足つきとして渡せばそのまま持って帰ってくれる。衛兵は足つきを捕まえたいんじゃなくて、捕まえたという事実がほしいだけだから、本人確認とかない。だからなおさら仲良くする。足つきってことにされて連れてかれるのは誰だってごめんだから。お忍びはこのへんの相場を知らないから無雑作に金をばら撒く。たまにお忍びを目の敵にして襲いかかろうとする奴もいるけど、周りの奴から死にたくなるまで殴られるからすぐに諦める。足つきやお忍びがいなくなるといつものスラム街に戻って、さっきまで肩を組んで歌い合ってた奴らも殺し合う。殺伐として卑屈な街だ。それはスラム街って名前にも現れている。
いつだったか、お忍びが忍ばずにやってきてご飯を配ってたときにいた若い女(あれはきっとシスターとかいう女だった)が、「スラムという名前の街なんてありません、あるのはそう呼ばれるほど飢えた街とそう呼ぶ傲った人間です」とよくわからないことを言っていた。その女は夜のうちにぐちゃぐちゃになって死んだ。こんなところで寝泊まりしようとするなんて、確かにお金持ちの趣味はわからない。ここはスラム街なのだ。のけ者が集まって群を成し、気がついたら街になっていただけの、ほんとうに名前なんて無い街だ。皆んな適当な呼び名をつけて、Get to hとか、Ghostreetとかって呼ぶ。でもどんな呼び方をしたって、ここはスラム街で、皆んなうっすらとそれがこの街の名前だとおもってる。ピュートとおそろいの名無しの街。
ピュートには名前がない。呼ぶような物好きもいないし、個人を識別する符号は必要ないから。スラム街の孤児、死に損ない、かたわ、そういうので十分だった。だからピュートは自分の名前を知らないし、自分でつけることもしなかった。ピュートには所属がなくて寄り合いの家族がいない。正真正銘の孤児なのだ。そんな生き物の名前なんて誰も気にしない。ピュートというのはかたわの別名だ。ご飯を配ってた女が、かたわを見るたびに言っていたのだから間違いない。あの女は言葉が幼かったからまともな会話はできなかったけど、ピュートが自分を指さして繰り返すと頷いていたからあってるんだろう。かたわよりもそっちのがちょっと素敵におもえて、ピュートはピュートと名乗るようになった。ピュートだってそういうお年頃なのだ。正確な年齢なんてわかりゃしないけど。
お喋りなおじさんはピュートをteensだと言った。いまの買取人は死に損ないの大人だと言って、目の前に転がってる女は、両手足の指くらいだと言った。きっとピュートは全部の指と少しぶん生きていて、とっくに大人なのだとおもう。転がった女が言うには、ひょろながくて、犬みたいな声で、よく食べる、ガラクタみたいな男らしい。変なとこから腕が生えているし、ざんぎり頭はそもそも髪がないとこもある。女はそんな傷だらけの頭を抱えて、「お屋敷に帰ったら飼ってあげる」と言ってわらう。捨てられたことを知らないらしい。よく自分の長い方の名前(家名というらしい)を叫んでひとしきり騒いだら、「ははさま、ととさま、わたくしはここにおります」と唸りながらちいさくなって泣き出す。いまもそうだ。あんまりうるさいと殴られるし、ましてお前は女だから酷いことをされるぞと教えてやるのに、ちっとも聞きやしない。この女もたぶん、頭が足りないんだろう。あときっとピュートより生きてない、teensの女だ。
だからピュートは自分の住んでいたぼろ家の隙間という隙間に布を詰め込んで、めったにしない繕いものをして女を包めるくらいの布を作った。泣き疲れてその場で寝るくせに、放っておくと寒いといって泣くのだ。最近は女が泣き出したら座って布を広げるようになった。そうすると女はちいさく転がったまま器用に移動して、布越しにピュートに体当たりして抱きしめられるのを待つ。膝の上で震える女を抱きかかえてやると、さっきまでの絶叫が嘘のように大人しく寝るのだから驚きだ。布で包まれている女は赤子のようで、ますます幼く見える。ピュートは気がつけば一人で、一時的に庇護下にはいることはあっても家族になることはなかった。しかしこの女はつい一ヶ月前まで、ははさまと、ととさまと、ねえやと、指折り数えるほどの大人数で生きてきたのだ。誰かの、家族だった女。