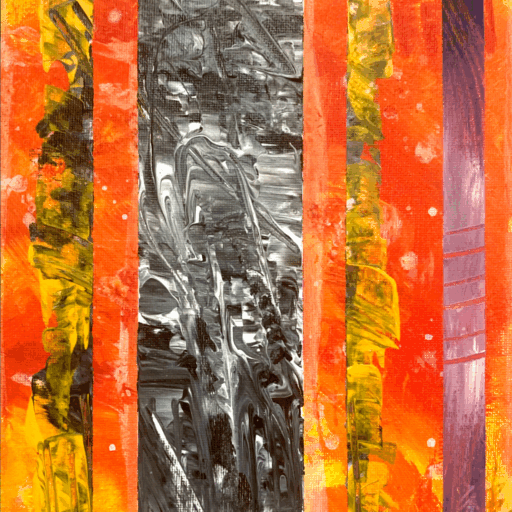よくある話だ。お忍びの家から金がなくなったときに、一番最初に捨てられるのは血の繋がりがない奴、その次が血の繋がってる出来損ないだ。この女は頭が足りないようだし、きっとねえやの方が要領が良かったんだろう。女の話にはいつもねえやを褒める親が出てくる。自分の家族の自慢をするくせに、自分と家族の話はしないから、女はお屋敷に住んでいたころから一人だったのかもしれない。ここじゃ考えられないことだけど。スラム街で生きる奴らにとって、血の繋がりなんてものは大して重要じゃない。大事なのは一緒にいて生き延びられるかだ。足が遅くても、短気でもいい、集団でいる理由は命を取りこぼさないためだ。臆病な奴がいなきゃ勝手に自滅していくし、乱暴な奴がいなきゃ取って食われて死ぬ。死に損なった大人は、子供を生かすために存在しているのだ。そういう寄り合いを家族と呼ぶ。もし女の生まれがお屋敷じゃなかったら、捨てられることもなかったのに。そうしたらピュートを家で飼うこともできたかもしれない。だって女は、頭が足りないけど手先が器用で、料理だってすぐに覚えたし、愛嬌があるから近くに住んでる老人にかわいがられている。泣く喚くことも多いけど、それだって抱きしめてやればすぐに治るのだから気にならない。いまでこそ触れ合うのはピュートだけだが、この街に生まれていたならいろんな奴に抱きしめられて、きゃらきゃらわらっていたに違いない。生まれの不幸ってのは、金の有無じゃないのかもしれない。
女の生まれた街は華やかな暮らしをしている人間ばかりが住んでいるらしい。名前も大層お綺麗で、高名な学者の名前を付けられていると言っていた。「そんな学者になりたい」とも。捨てられる前は頭が良かったのか、足りないことを教えてくれる人がいなかったのか。ともかくその高名な学者とやらは、貧富の差の話をして、金の有無で役割の違いを語った経済学者で、女はその考えにいたく感銘を受けたそうだ。ピュートは近所の老人が悪態をついていたことを思い出したが、口には出さないでおいた。言わなくていいことを言うと、肉屋に並ぶ羽目になるのはよく知っているから。
老人はその昔、権威ある学者に楯突いた罪で職場から追い出され、石を投げられながらこの街に来たと酔った勢いで語った。この街には人間街で嫌われたから来たという奴が多い。そういう奴らは自分の生まれた街を憎みながら、羨んで生きている。スラム街生まれのピュートみたいな奴にはわからないことだ。人間街の名前なんていちいち覚えていないし、この街に執着なんてない。老人は自分の生まれた街を能無しどもの墓場だと呼ぶ。ピュートにはその言葉が、自分の死場所はあの街だ、と言っているように聞こえた。けど老人はもう諦めていて、この街で死ぬ未来を受け入れているらしい。ピュートが熱を出して死にかけていたときに、わざわざ家にあげて、お粥を煮込みながら話ていた背中を妙に覚えている。スラム街ができたのはその学者のせいだと怒りながら鍋をゆすって、「貧乏人の役割なんぞ決めよったから国が膿んでいったのだ」と吐き捨てた。できたお粥をピュートの枕元に置いてさっさと寝たから、詳しいことは聞けてない。翌日には熱が下がっていて、礼を言ったら返事はなかったけど、一度だけ目があった。それきり老人の家には行ってないけど、女が顔を出すようになってから少しずつ喋るようになった。女は老人のする話がすきらしい。老人も女には墓場の話じゃなくて職場の話をしているようだった。
「今日はどんな話をしたんだ」
「ねえや、わたくしここにいるわ、生きてるの、おむかえ、おむかえを」
「ご飯はもう食べたな? 明日のスープの具は三つだ、おまえはにんじんがすきだろ」
「にんじん、にんじんを、たべれるのよ、ととさま、わたくしなんだって、たべれるわ」
「こら、そっちに転がるな。寒くて泣くのはおまえだろう」
「ははさま、わたくしね、ししゅうもできるのよぅ、おようふくも、なおせるのに」
「だめだ、爪を剥ぐな。痛くて泣くのはおまえだろう」
ピュートは手間のかかる女に手間をかけてやって、なるべく泣かなくて済むようにしてやる。老人は女の声を鳥の囀りのようだと言ったが、泣き声は正しく鳴き声のようで、それも縊り殺されるときのような頭に響く声なのだ。そのうちに枯れて隙間風のような声になってしまうんじゃないかと心配になる。そうなったら「こんな声じゃお迎えがこないわ」とか言って泣くのだろう。それを宥めるのもやっぱりピュートなのだから、この女はとてつもなく世話の焼ける生き物なのだ。やっぱり、女を拾ったのが自分でよかった。家には子供も老人もいないし、ピュートは大人になるまで生きてこられた利口な人間だから、正気のときはしゃんとしていられる女を一人くらいなら養うこともできる。女はピュートの膝の上でおくるみに包まれた赤子みたいにあやされてもちもち抵抗している。今日は一段と意志が固いが、こんな夜更けにこんな柔らかな女を外に出すことはできない。ピュートには生き物を拾った責任があるのだ。なるべく長く健康に生かすこと、それが自分を殺すことになっても。いつか出会った犬を飼っている男が言っていたから、ピュートはそれに倣って女を生かしている。布にゆるく拘束されピュートに抱きしめられた女は、ようやっと諦めたのかぽそぽそ泣き言を言いながらも大人しくしている。
「だってね、わたくし、かえんなくちゃ。あなたを、かうのよぅ、そうでしょ」
「はなせ、布を齧るな。穴を塞ぐのは俺なんだぞ」
女は自分やピュートの服は勝手に繕うのに、この布だけは言っても手をつけない。これはどうしてかピュートの仕事として割り振られているようだった。いーっと駄々っ子の顔をする女の前髪をあげてそのまろい額に口付けをひとつ。女はぱちり、瞬きをしてそのまま寝た。女がどうしても寝ないときの最終手段で、なにか特別な儀式だった。理由はわからないけれど、ピュートも女も安易にこの行為を望まなかった。ピュートはもしかしたら娼婦の安く売られた唇を思い出しているのかもしれないし、もっと昔の思い出せない母をなぞっているのかもしれない。あるいはそれらも全く無関係なのかもしれない。初めにねだったのは女だったが、それ以来はっきりと欲しがることは一度もなく、またピュートを拒むこともなかった。女を抱えたままその場に寝転がる。ぴすぴす鼻詰まりの寝息を立てる女を見ていると自然に瞼が降りてきて、乱した前髪を整えてやってから眠った。
「ぴゅーと、おきて、起きてよぅ、動けないわ」
「あばれるな、けがをして、なくのはおまえだろう」
「おまえじゃないわ、ザッカリー。忘れちゃった?」
「あぁ、しってる」
「ピュート、起きて、ねぼすけさん。くるしいわ」
覚醒しきらない頭を回して腕を退ける。寝返りを打つピュートの耳にいくつか小言が飛び込んできたが無視して二度寝する。だって女は太陽が昇り始めてすぐに起きる。一人暮らしのときは昼過ぎまで眠ることもあったピュートにとっては考えられないほどの早起きだ。それにピュートは女の夜泣きのせいで遅くまで起きているのだから付き合ってられない。女の頼りない足音を最後に意識は落ちていった。
「ピュート、起きて!」
「んぁ、かいほう、してやったろう」
「大事なお話があるの、ちゃんと聞いてほしいことよ」
「あー、わかった、おきる」
いつになく正気の声に違和感を覚えながら起き上がると、女は背筋をのばしてしゃんと立っていた。手を引かれてテーブルにつくと女がなにかを言った。ごぽごぽ、溺れているような音がしてなにもわからなかった。ピュートが聞き返すと女は口角をあげて、身を乗り出して言った。
「お迎えがきたのよ」
「そうか」
「お祝いしてくださいまし」
「よかったな」
「ええ、とっても!」
言うが早いか女は軽い足取りで玄関まで向かうと、そっと振り返ってピュートに一礼した。そして埃と家鳴りばかりのボロ小屋を飛び出したのだ。目に眩しい黄色のスカートがよく似合っていた。扉が閉まる寸前、表にいた馬と目が合った。女を乗せた馬は軽快な足音を響かせて人間街へ向かう。ピュートはその音を聴いて安堵したのだ。女はもう、安心して大声で泣ける。もう二度と捨てられなきゃいい。
「よかったなあ、よかった」
「なにがよかったの?」
「は? なっ、んで、おまえ」
「ザッカリーよぅ、わすれんぼうさん」
見慣れた女がピュートを見下ろしている。ピュートはテーブルについてなんかいなくて、女は黄色いスカートなんかはいていない。混乱したピュートが両手で顔面を包んで揉みくちゃにしても、困惑しつつわらうだけで溶けたり崩れたり消えたりしない。本物だ。であればお迎えは、来ていない。悠々と駆ける馬も、ははさまもととさまもねえやも、なにもないのか。ピュートはどうにも耐えられない気持ちになって深く、深く、ため息を吐いた。
「わるいゆめだったのね」
「いいや。いままでで一番、そう一番に、良い夢だったさ」
「じゃ、どしてそんなお顔をなさるの」
「夢だったからだ」
「さみしい?」
「それは、ザッカリーだろう」
「ふふ、覚えてくだすったの、ならちっともさみしくないわ」
そしてピュートは気づいたのだ。女が、ザッカリーがただの一度も、寂しいと言ったことがないと。いつも寒いだとか痛いだとか、怖いだとか言って泣く。素直で透明な女だと思う、だからこそ痛々しい。ピュートにとって寂しさとは喪失の象徴だった。抱えていたものが腕の内からなくなってしまったときの、やるせない気持ち。ザッカリーが本当に寂しくないと言うのなら、それはザッカリーがお屋敷でさえ一人だったことの証明のようじゃないか。帰りたいのだから、帰るのが一番だと、ピュートはいつまでそう言えるだろうか。ザッカリーがわらっている。明け透けにわらっている。
「おなかは空いているかしら」
「空いてる」
「ごはん食べましょう、昨日のパンが残っているわ。あなた昨夜は食べなかったのね?」
「放って置けなかったからな」
「わたくし、またうるさくしたのね! ごめんなさいピュート、怒ってるかしら」
ザッカリーは夜泣きしたことをすっかり忘れてしまうようだった。ときどきうっすらと覚えているが、そいう日はずっとぼんやりしたままお屋敷の話をする。そのときばかりはピュートも外に出るのをやめて、布で包んだザッカリーを膝の上で撫でながら虚ろな話を聴くのだった。
「いつものことだろう。いまさら怒らない」
「いつも、そういつも、泣いちゃうのよぅ」
「パンを食べるんだろう」
「そう、パン、食べなくちゃ」
パンと共にあたたかなスープを食べる。豆と芋が入った塩味のスープだ。今夜はこれににんじんも入る。ピュートだけが食べるなら芋もにんじんも入らないし、なんならパンだけかもしれない。まともな食材が手に入るようになったのはザッカリーがやってきてからだった。市場は人間街に近くてあまり近寄らなかったし、気味の悪い見て呉れのピュートに素直に物を売ってくれる店はない。客が来なくなるから失せろと棒切れで追い払われたことも多々ある。だが一度ザッカリーと一緒に行ってからはそんなこともめっきりとなくなって、まるで普通の形の人間のように扱われるのだ。ザッカリーは肉屋に怯えてしまったからその一度以降はまたピュート一人になったが、今日まで邪険にされたことはない。
「今日はどこまで行くの?」
「北の回収所から、西の四番目の通りまで。あー、肉屋に、納品に行く」
「買って帰ってきちゃいや」
「俺は人の肉は食べない。あれはひどい味がする」
「たっ、たびたのね」
「たびた。おまえ、ザッカリーが、よくしがみついてる腕に傷があるだろう」
「ざらざらのところ?」
「そうだ。そのざらざらは俺が自分で削いで食べた跡だぞ」
「ひゃぁ」
半開きになった口を震わせて驚いているザッカリーに下の腕を見せつけてやる。ほら、これだぞ。ザッカリーは下唇を噛み両手で頬を押さえて、いやですという表情をした。ちょっと意地悪するとすぐこうなる。それがおかしくてピュートは背を反らして笑ってしまうのだ。
「美味しいスープを作るわ、だから二度としないでくださいまし」
「材料を揃えるのは俺だろう」
「わたくしだって」
「いや、だめだ。駄目だよザッカリー、おまえは脆いから」
「おまえじゃ、ないわ」
「ごめんな」
「ゆるしてあげる」