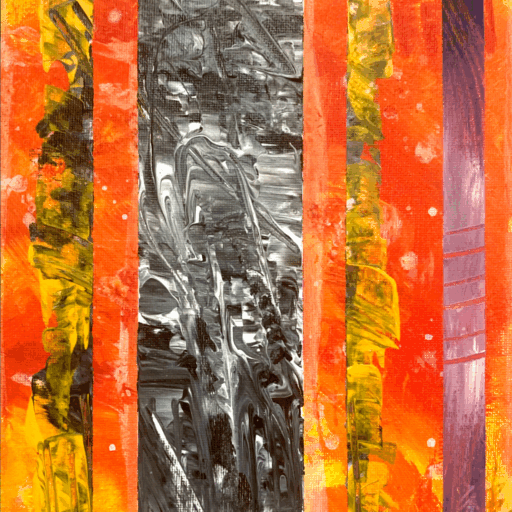小説 玄関 晟陽
「にしてもあのご令弟様とねぇ」
「あら、ご当主様よう!」
廊下に落ちる影は長く、薄く、日向と日陰のあわいを曖昧にしていた。微かに残る線香の匂いが、なけなしの矜持のように思えて。歩みを止めることを許さなかった。
「いけないわ、気をつけなくちゃ。そうそれで、奥方様ねぇ、あれほど先代様によくしていただいたのに……」
「いい? 言わなくていいことと、言っちゃいけないことってのがあるのよう、その話はその両方!」
女中共の姦しいものだ。つい先週に父が亡くなったというのに、屋敷はひどく浮ついていた。黒から白へはっきりと、これが正解だとでも? 母はなにを考えているのか、さめざめ泣いたのは父の亡骸と初めて対面したときばかりだ。それから数時間後のあまりにも早い葬儀の時にはもう頬を艶めかせていた。決して涙の跡などではなく、弱ったふうを気取って、叔父を侍らせて。ついには今日、母は叔父と籍を入れた。”元から家族だったじゃない”、”何が変わるわけでもないの”、”まだ、父さんと呼べないのもわかるわ、焦らなくていいのよ”。なんと、愚かな女。瞬きの内に主張が反転するのだ。不変を嘯いて一息、二言目には取って付けた続柄で呼べと。私の父は、生涯変わることはない。海津宗太郎、ただ一人だ。
父の書斎へつながる階段を一段ごとに踏みしめて上る、上って、終わりの一段。境界を示すように張られた黒檀の無垢材、その上に立ち振り返れば。父が死んだ景色だ。私の背後から、肩越しに父が見る。耳の縁を掠めて突き出された指の先に、軽薄さに布を被せたような男が一人。
“あれが怨敵だ”
そうであろうとも。
「叔父さん」
「……どうした、危ないぞ、そんなところで」
「こんなところで、私の父は亡くなったのですね」
「おまえが、受け入れ難いのもわかっているが……弘美さんだって前を向こうとして」
「ご結婚おめでとうございます」
影の薄く、遠くまで。父よ、そこで見ていればいい。もうじきに踏板も蹴込板も側桁も新に張り直される。父よ、あなたの痕跡は血の一滴でさえ残らない。重苦しい黒檀の無垢材など、あなたの仏間を飾るだけだろう。父よ、そこで見ていればいい。ただ生きていく、私の生き様を。