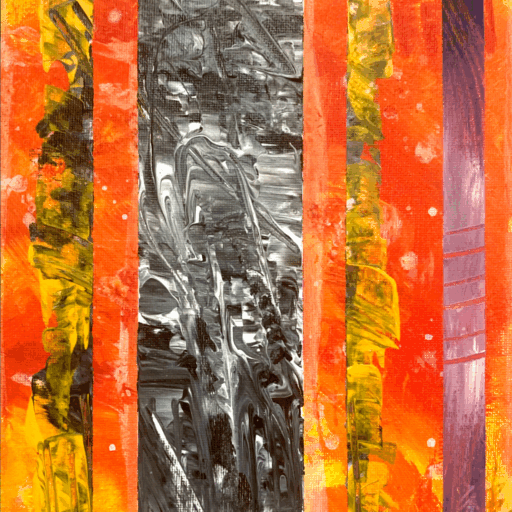小説 玄関 晟陽
娘が小桜と名付けられた。艶やかな葉のざわめく夏のことだった。
「ぅああ、う、ッわぁう、きゃーぁはは」
「よいこ、よいこ。わたしの桜」
頭皮につん、とした痛みが走る。桜子は揺れるものに興味津々で、よくわたしの垂れた髪を掴んでは引っ張った。ふやふやの指に絡むといけないから、楽しそうなうちにそぅっと手を広げさせる。桜子が気に入ってくれたから、ちゃんと梳っているの、わかるのかしら。
「うるせぇぞぉ錫子! 早よぉ黙らせ!」
最近は手遊びが好きみたい。ぐー、ぱー、ちいさなおててがちいちゃくなって、おっきくなって。
「おっきくなってもちいさいものね、んふ、っふふ、かぁわいい」
「ふひっ、んひっ、ふ、ふぁー」
ふっくらした手のひらを指先でくるくるすると、ぎゅむっと掴まれる。骨が軋むくらい強くて、あぁ、生きてるのね。こんなに嬉しいことって他にないの、ほんとうよ。世界のここにしかないの。勇さんと一緒になったときだって、これほどの幸せはなかった。わたしの桜、まだ人間じゃなくって、神様に近くってこんなに、生きてる。舌のもつれた笑い声も、足を見つけて咥えるのも、そこらを涎でぺしょぺしょにするのも、なにもかもかわいくって幸せよ。お膝におろして背中を支えて、水袋のような胸元にこわごわと耳を寄せた。
と、と、と、ふぅ、ふぅ、くるる、きゅる、あぁーう、ぅあん。
「かあさんのこと、撫でてくれるのね……」
「んわぁ、あ、うぅあ! きゃーぁ、ッあぅ!」
うずくまってこうして、心臓と、肺と、お腹と、喉と、桜子が生きてる音を聴くとどうして、泣きたくなるの。ぽてぽて頭に当たる手のなんてやさしいこと、愛しいこと。丸ごと全部が命そのもので、わたしずっとあなたに会いたかったの。しわくちゃだったのがもっちりして、とろんとしてた目がぱっちりして、ぐらんとしてた頭がしっかりして、ちゃんと人間になっていく。きっとすぐにお喋りするようになって、自分で座って立って走って、泣くのも笑うのも好きにできるようになる。わたしの桜、散ることなく永遠を願ってしまうけれど。あらゆることが、あなたの望み通りであればいいと思うの。
「それだけ。それがかあさんの全部なのよ、桜子」
神様、いつだか聞いたことがあります。魂には目印があるのだと。真名というらしいそれは、いったいいつ定まるのでしょう。いちばん初めにつけられた名だというのなら、やっぱりこの子は桜子なのです。どうか惑わず、見失わずにいてくださいまし。わたしの桜を、山瀬桜子を。
「錫子! そんなもん納戸にでも閉じておけ! それより薬と茶ぁ、さっさと動かんか!」
脚の悪い萎びた爺が、声だけ張ってなんになるという。尺取虫のように這いずるが精々。そんなことよりも、かわいいかわいいわたしの桜。雷だって、ぽーっとみてはきゃぁと笑う子で、怒鳴り声なんて気にも留めないみたい。こわがるようなら納戸にでも閉じておこうと思ったけれど、萎びても枯れても人は人、運ぶのも一苦労だったろう。わたしに似て気丈夫な子。
「よいこ、よいこ、わたしの桜。ふふふ、すぅー、はぁ、あまいお乳のにおい……んふ、涎のにおいもする」
お天道様の朗らかな光に温まって、心地よさそうにまどろんでいる。
「ねんねん、ねんねよ、あったかいね」
お昼寝日和だもの、たくさんお眠り。夜に眠れなくっても、かあさんはずっと一緒よ、お月見しましょうね。