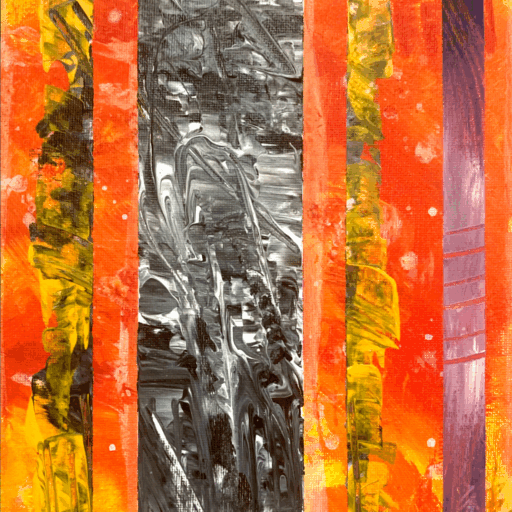小説 玄関 晟陽
無理を言って東京の外れにある全寮制の高校に入学した。親がきらいなわけじゃない、地元がきらいなわけでもない。ただ離れたかったのだ。私はきっと一人でやっていけると、私ならどうにかなると、そんなことあるはずがないのに。過信していた。慢心していた。あまつさえ心配して度々連絡を寄越してくる親に人形扱いするなとさえ思っていた。私には親のその愛に満ちた言葉が、子供をいいように操作しようとする悪しき言葉に聞こえたのだ。ほんとうに悪意に満ちていたのは紛れもなく私だったのに。わざと酷い言葉として受け取っていた私が一番根性悪であった。
喧々轟々とする烏合の衆に紛れ潜むばかりの今世で、夜毎よりいっそうあの子のことしか考えられなくなっていた。行くに行けず帰るに帰れず。
私は自分を、“すごくできる子ではないが、それでも三番目くらいにできる子”だと評価していた。けれどこの文言は一割ほど間違いで、文頭に“田舎では”と付け足さなければならない。私の過剰な自尊心は高校入学から一週間で爆散した。膝をつき四方八方に散らばる破片を必死になって集めて、やっとのことで継ぎ合わせて、どうにか私は人の形を保っている。中身なんぞみんな流れてしまった。今頃は用水路で混和して自然を潤わせていることだろう。だが中身がなくては、思想を持ち目的を作り行動しなくては、少なくともそういうふうにしなくては、誰も私を見やしない。私だってそうだ。思考停止し言われるがまま従順であるだけの人間なんて、それこそただの人形とさして変わらない。そんな奴より、打てば響くように出し惜しみなく自分の意見を伝えてくれる人間のほうがずっと魅力的に感じる。私は結局誰かと一緒に生きたいのだ。それもとびきり素敵な私が好きな誰かと。
口にするのは容易いけれど、掻き集めた言葉を尽くせばどうにかできるほど、私の情念は簡素な形をしていなかった。来る日も来る日もひたすらに、思い耽ることしかできなかった。
何が一人でやっていけるだ。ずいぶんな啖呵を切ったものだなあ、そのまま勘当切られてしまえばよかったものを。なんだってこんなに甘え腐っている。自分を嘲っている今だって、ともすれば親を「こんな奴にまだ心を砕いているなんて、おまえたちのそれは偽善だろう、さっさと突き放してやれば立ち直れたものを。飼い殺しじゃあないか」などとだらだらと口汚く詰ってしまいそうだ。そんなことをすれば、善良で愛情深い彼らのことだから、永く傷心の日々を送るだろう。その惨い傷はどうしたって癒えず残り、母は痛哭し、その声は父を串刺しにして哀愁に沈めるだろう。わかっている。尊厳を踏みにじり愚弄する鬼畜のような所業であると。わかっている。きっと私の想像は現実からそう大きく外れていないし、なんなら実際もっと悪いかもしれない。けれどそれを、少し望んでしまう私がいる。私は恐ろしい。私が恐ろしい。私の親への愛情が、尊敬が、信頼が、いつしかこの得も言われぬ加虐欲に塗り潰されてしまうかもしれない。最悪の未来に慄き心臓が逸る。そうなったら私はどうする。回る感覚と共に血の気が引いていく。私はいったい加虐の先に何を得る。目の中で線香花火が爆ぜる。
光に混じって見えてしまった。憎悪と、侮蔑と、疑心と、優越感に浸る私を。肺腑をぐちゃぐちゃにしながら、それでも衝いて出た言葉を撤回できずに自分の言葉に翻弄される私を。人でなしの私を。
「なにしてんの」
ぱんっ、と張りのある声と独特の空気を纏う言葉に、いつのまにか締め付けていた喉を緩めた。彼女の口調は流暢なはずなのに、語末の一文字がころりと落ちるような奇怪な印象を抱かせる。それは腹の底で膨らむ残虐さから気をそらすのに最適で、私は努めて彼女の喋りの違和感を拾った。
「考えごと、少しっ、だけ」
咽せる手前のような勢いのついた返答になってしまったが、彼女はたいして気に留めなかったようだ。
「そうか、それじゃ次は明日のわたしの予定を考えてくれ」
彼女は度々、唐突にこういうへんなことを言うことがあった。自分の行動を何故だか私に決めさせるのだ。それは明後日に読む本だとか、来週の月曜から土曜までの食事だとか、来年に歌う曲であったりした。
「何を食べるかとか、そう言うこと?」
「明日の予定だ。そのまま、明日一日の予定だよ」
これは予想がつかなかった。私は既に何度か彼女の予定を決めてはいるが、それは読書や食事など何か一つのことについてだけであったし、明日の予定をまるきり決めるなんてしたことがなかった。それに明日一日と言ってもどこまで決めればいいのかまるでわからない。
「起床時間から決めたらいいか? それとも大雑把に」
「起床時間から決めてくれ」
問いを遮って私の言葉をそのまま使った彼女からは、仄かに興奮しているのが見て取れた。先走って開いた口は落ち着かずまた文を繋ぐ。
「何時に起きて、何時に着替えて、何時にお手洗いに行って、それから」
「待ってくれ、私はそんなことまで決めるのか?!」
今度は私が彼女の言葉を遮ることになった。私の激しい動揺が伝わったのかいないのか、一拍ほど置いて彼女は言った。
「んーと、そりゃあ、そうだろ? だって、なあ」
そんなわけあるか。いつも軽快に返答する彼女にしては妙に歯切れが悪い。何か後ろめたいことでもあるのか。
「だってなんだ」
「だってその、おー……下名と君は、おともだちだろ?」
彼女は意図して胡散臭い雰囲気で振る舞った。戯けて追及を逃れようとしているらしい。
「私はおともだち相手に下名なんて一人称使わないと思うぞ。少なくとも何か企てていたりしない限りは」
「企てるなんて、そんな大袈裟なことしないさ」
心外だとでも言うように彼女はそっぽを向いた。茶化して誤魔化すには、彼女は僅かながら正直過ぎたようだ。
「何かはするんだな」
「う、うぅ、うぎゃー」
これじゃ自白したようなものだ。“うぎゃー”というのは彼女の鳴き声で、これは彼女が“かいじゅう”になったときの合図のようなものだった。追い詰められたときや暇なとき、たんに機嫌が悪いときなど理由は様々だが、彼女は時折大きな口で鳴くのだ。曰くかいじゅうになることで不満をより鮮明に表現できるのだとか。私は彼女のこの手の不思議理論が大好きなのだった。ともかく、彼女がこの鳴き声を発したということは、やっぱり何かを画策していたらしい。きっとまたどこからかろくでもない知識を付けてきたのだろう。前から彼女にはそういうところがあった。
私は「はあぁ……」と当てつけらしくため息を吐いてから「何をするのかくらい言いなさい。事によっては協力してあげるから」となるべく優しく言った。すると彼女は「なにもそんな、あやすみたいな言い方しなくてもいいじゃないか」と小さな口でか細く呟いた。なるほど、彼女は今あやされていると。なんて可愛らしいのだろう。私が喉を迫り上がる笑いを噛み殺すと、それを目敏く見つけた彼女が「わたしは幼児じゃあないし、君にそんな宥められる筋合いはないし、だっていつも通りのお願いだったろ、別にさ」なんて独りでにぽそぽそ言い訳を始めるものだから、ついに堪えきれず笑い出してしまった。
「なんだよ」
「なにもっ、ふふ、言ってないよ」
「笑ってるだろ」
「かわいかったから」
私が素直にそう言うと彼女は面を食らったようだった。「……か、わい?」と自分を指して訊ねてきた。これじゃ私は可愛いかと質問するいじらしい少女のようだが、全く気付いていないらしい。だから私はわざとゆっくりと「うん、かーわいい」と言ってやった。
「どっ、同意を求めたわけじゃない! わかるだろ!」
流石に理解した彼女が慌てて否定してきた。そう過度に焦って語気を強めるほうがかえって怪しいものなのだが、耳まで真っ赤な彼女はそれどころじゃないらしい。絶対教えてやらない。彼女は言葉の裏を読むのが上手で、物事を多面的に捉えるのが得意だ。だがそのかわり打算のない率直な褒め言葉に弱かった。それはそれは弱かった。
「わたしが、かわいいってなんで」
「だってあやされてると思ったんだろう?」
「現にあやしてただろ!」
「私はおともだちに対してできる限り協力してやりたいと思っただけだよ。それをあやされていると思ったんなら、君はあやされるようなことをしていると、いつも通りのお願いが我侭にもなり得ると認識していたわけだ。ほら、かわいいだろう」
もとより何かを要求することはなにも悪いことではない。他者とのコミュニケーションはこうして欲しいああして欲しいという欲求から始まるのだから、それは得手して必要なものだ。だが我侭はいけない。これは全くいけない。そもそも我侭と頼み事の区別が付いていない輩が多すぎる。たとえそれがどんなに無茶な要求であっても相手が快く受け入れてくれればそれは頼み事になる。しかし相手がきっぱり拒んだにも関わらず利己的な姿勢で要求を押し通さんとするならば、それは我侭であり罵倒されて然るべき行為だ。そして我侭を頼み事にするためには、要求をなるべく好意的に引き受けてもらえるよう言葉巧みに説得しなくてはならない。彼女はそれをよくわかっているし、だからこそかいじゅうになった。
けれど私はそれを嬉しく思う。有象無象の我侭なんぞ死んでも聞かんが、こと彼女になると話は別だ。どうも彼女は、我侭がいけないことなのは知っているが、我侭が受け入れられるとそれは甘えとなることは知らないらしい。私は彼女が甘えられる稀有な存在になれたことが、なんだかとても重要なことに思えて、苦しいくらい嬉しくなるのだ。そんな心情が顔に出ていたのだろう、彼女は“かわいい”という評価についてそれ以上何かを言うことはなかった。
「で、何をするんだ?」
「言ったら怒るだろ」
「さあ、それはわからないな。怒るかもしれないし、拗ねるかもしれないし、聞いてみなきゃわからない」
「嫌われるかもしれない。もしもわたしを嫌うことがなかったとして、でも内容は、絶対、嫌いだろうから」
余程のことをしようとしているのか、それともそれは私のいわゆる地雷というやつなのか、どっちにしろ彼女にとってはそれほどのもののようだ。
「焦ったいのは嫌いだ」
嫌いというのを強調すると彼女は「うぎゃ」と短く鳴いてぎこちなく話し始めた。
「じゃあ説明、するけど、も、元ネタは、あー、スタンフォード監獄実験って、あるだろ」
「私が看守役か、はぁ。私が演技に引っ張られて君を虐待するような人間だとでも?」
半ば無理やり言わせたのは私だというのに、反射的に嫌悪感剥き出しの答申をしてしまった。どうやら彼女のお願いは私の地雷を見事に踏み抜いたようだ。それも一番たちの悪いものを。そのことに、なんとも的外れな失望感を抱く。けれどここまで不快に感じたのは先程の考えごとのせいもあるのだ。普段の私なら顔を歪めてため息ひとつで流していただろうが、今の私には図星を突かれたような気がしてならなく、要はこれはただの八つ当たりでしかなかった。
「違うぞ、違う。君のじゃなくて、わたし自身の変化が知りたいんだ」
「私は君に調教を施す気はないよ」
精一杯明るい声を出したが、突き放すような口調になってしまった。それに対して「ばか!!」とシンプルに悪口を言った彼女は「そういう趣味の話じゃあない。ただ気になるんだ」と言い、少し真剣な顔になって続ける。
「看守役がエスカレートしていくのは理解できるが、なぜ囚人役は抵抗できなくなっていくのか。いろいろ考察も理由も読んだけど、納得できなくて。私なら看守役を殺して見せしめにしてやる自信があるし……似たようなことをすればわかると思ったんだ。どうしても、知りたくて」
彼女は好奇心が旺盛で、一度浮かんだ知的欲求は満たされるまで脳裏を漂うことを私はよく知っていた。だから彼女の実験にはできる限り協力してやりたいとも思っている。そのために私は、できるだけ冷静な声色でこの実験の最も重要なことを確認した。
「いつも通りのお願いも、この実験の模倣だったのか?」
もし、万が一そうであったなら、私は彼女を虐待するだろう。妙な確信があった。それはけして肉体を虐げるものではなく、彼女の中にある私への好意と罪悪感を利用して被害者として加害するという、より卑劣なやり方で。その先で彼女に殺され、野晒しにされるとしても。
「違う。君とわたしの名誉に誓って断言するよ。そんなことはあり得ない」
向かい合って真っ正面。見据えた彼女の瞳にはいっぱいの誠意が浮かんでいたが、無視できないほど滲んだ後悔と物寂しさが翳っていた。こんな痛々しい表情をさせたのは私なのだから、私に同情する権利なんぞない。それでも心臓が硬直し肺が重く沈む。
「……わかった。協力するよ」
「いいのか?」
「ああ、君と私の親愛に誓ってね」
目を合わせたまましっかりと返事をすると、彼女はあからさまにご機嫌になった。窮屈だった空気が一気に華やかになり、私は穏やかな気持ちで彼女を見つめた。
「でも、本当に付き合ってくれるのか? 自分でもその、この実験を君に持ち掛けたのは、我侭だったと思っているし」
彼女は口角をきゅっと下げて顔色を伺ってくる。勝手に裏切られたような気になって苛立つ私のほうが何倍も我侭だというのに。やっぱり彼女は特別かわいらしい人間なのだ。
「今日は、いや、この件に関しては、君を甘やかすと決めたんだ」
「名前も覚えていないのに?」
あっけらかんとした様子でずいぶんと今更なことを指摘され、言葉に詰まってしまった。こういうとき何と言えばいいのだろうか。彼女も別段気にしているようには見えないし、そんなに深刻なことではないのかもしれない。けれどそれならわざわざ口に出すだろうか? 彼女が? 考えにくいな。
「んーと……覚えたほうがいいのか?」
たっぷり一分考えて絞り出した答えは、素直に本人に聞くというどうしようもないものだった。そして彼女は「そりゃないだろ」と即答した。当たり前のように言うものだから、少しやけになってしまう。
「でも君のことを覚えてるだろ、可愛がってもいるし、ちゃんと今私と対峙しているのは君だって認めている!」
吠えた私に彼女はどうしようもないとでも言うふうに「頑張って?」と小首を傾げた。
「そりゃあ、頑張って」
「頑張ってる時点で、えー、どう言ったら、いいかな」
彼女は「あー」だの「うー、うぎゃ」だの無駄吠えしながら考え込んでしまった。どんどんと険しくなる表情を観察しつつ、彼女の言葉探しを待つ。それとなく「ダメなこと」を言った予感がするのは私の杞憂だろうか、それとも虫の知らせだろうか。もしかしたら私は彼女の地雷の上でタップダンスでもしたのかもしれない。それも一番たちの悪いものを! 眉間のシワが取れなくなるんじゃないかと心配し始めた頃、やっと適切な語彙を見つけたらしい彼女がゆっくりと口を開く。
「くそやろー、かな」
確かめるように呟かれた言葉は的確に私の心を削った。一呼吸置いて覚悟を決める。
「……詳しく聞いても?」
「頑張らないと今の今まで会話していた、なんならしている真っ最中のおともだちを存在すら認識できなくなるところとか、それをなんとも思っていないところとか、なのに可愛がってるところとか、というか可愛がってるなら名前くらい覚えろよせめて意識しなくても認識くらいしろ。それに——」
うぎゃー! 叫ばずにはいられない! 心の柔いところも硬いところも一緒くたにして鉋がけされている! 出るわ出るわ私に対する不平不満の数々。堰を切ったようにつらつら何の淀みもなく語る彼女は流石だ、立板に水とはこのことか。こんな状況で理解したくなかった。
「あとわたしのこの訴えを、心にはくるけどそれはそれとして改善する必要はない。とか思っているところとか、その他諸々、うん、くそやろーだと思うぞ」
ここまで来るとその他諸々も全て聞いてしまいたいが、心の安寧を自らドブに捨ててまで知った結果ただ私が傷つくだけなのは目に見えている。
「わ、わかった! わかったことにしたい! 見逃してほしい!」
「飛んで火に入ったなあ」
「うん」
「あはれなりや」
ぱっぱっ、払うように雑に頭を撫でられた。いっそ放って置かれた方がマシだ!