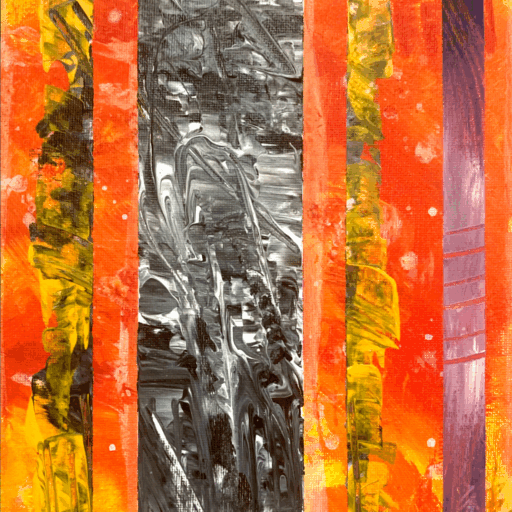さて、不思議な男ね。女は皿に積まれる掌にちょうどくらいのスフレパンケーキをふしゅふしゅ食べながら、あちあちの紅茶にマーマレードを溶かした。そうこうしているうちにもう一枚、ぱふっと落ちる。食べるよりも焼き上がる方が早い。向かいにある女のものより二回りも大きい皿には今にも崩れそうなほど堆く聳えている。縦結びのリボンが自在に揺れて、男の忙しない動きをかわゆく見せた。バターと小麦の香ばしさが小さなキッチンに充満している。時代遅れの白熱電球がスポットライトのふりをして、甘い食卓に従事する男を讃えた。おいしい朝食、偶然の産物。きっかけはベーキングパウダーがなかったこと。男が古い記憶からふわふわのケーキを焼く絵本を引っ張り出して、有り余るパワーで大量のメレンゲを作ってからはすぐだった。オーブンが壊れていたからフライパンを使って、生地を乗せる頃になって女が「どうせならかわゆいのが良い」って我侭を言った。ぢわぢわはしゃぐバターが落ち着いてもちんまり盛った生地は膨らまなくて、右に左に小首を傾げる男を、女は堪らないって顔で愛でながら紅茶を淹れた。男が初めてのお料理を冷める前に食べてほしいって甘えて、女が当然に甘やかしてやったらこうなった。絶対に食べきれないけれど、甲斐性ってもんは見栄と矜持でしょう。女はゆるんだ笑顔の内側に断固たる決意と愛を抱え、喜び勇んでフードファイトに参戦したのだ。
「風祐くん、お座りなさいな。それで最後でしょう?」
「まだ足ンねえだろ」
「自分のお皿に盛られたぶんは、頑張るわ」
「瀕死、なのかあ……?!」
今から絶望しますって顔で立ち竦む男の手を取って向かいの席までエスコートする。お行儀よろしく座らせて、自分の椅子をがたごと、隣に運んで食べかけの皿とぬるい紅茶を引き寄せた。ジャムを塗った一枚を等分して、大きなお口にまふ、と入れてやった。お腹が空くとバカんなるのよう、人間ってのはそうなの。女は軽快さに誤魔化されない確かな質量に挑みながら男をじっくり見た。不思議だ。女はいくつも知っている。一生に一度の大舞台で無様を晒すことのないように、もしもそうなれば、一生をこうやって過ごすのだと理解させるために。教育の体裁も保てない杜撰な虐待。齢四つから人権を代償にした手練手管を眺めてきた。翌朝になってどのような顔と声で、振る舞いで、言葉で、何を示すのか。既知のそれに当て嵌まらない男が好きだ。愛しいと思う。
「あいしているわ。わたくしの風祐くん」
「俺も! あいしてる、ひ、ひはは、ンへへへ。はるちゃん、かわいいなあ」
かわいいのだと、反芻する。電球のようで、破れてはならなくて、可愛い。そういう形をした、はるちゃん。御天道様の称えを持った、いはる。男の見る女はいつも一人、散散に鮮やかな閃光。
「きっと、かわいいでしょう」
かわいい、と告げられるたびに、平伏した男を視る。それは目玉だけで一抱えはあるであろうほどに巨大で、ぺたり、身を低く保っている。奇しくも、かえるに似通う様相で。見下ろすわたくしは燃える両手で、いとも容易く掬い上げるのだ。かわづ、河津。流るる水の湧くところだという。渾渾と、豊かである。一身に注がれているのだと自覚しているから、死ぬまで飛輪であろうと思った。動力源を考慮しなければならない工業製品ごときではちっとも足りない。この男の人生に落ちる影はひとつでいい。ぬらりと上背のある、やわこいくせ毛で、薄く小さい耳と筋張った大きな手足の。河津風祐、その身ひとつぶんだけでいい。
「はるちゃん」
「なぁに、風祐くん」
「舌、痛くねえ?」
「‥‥泣いちゃう、かも」
「ン、ぢぅ、あま」
心を配って、抱きしめようとしたら甘えてくれたから。歯型のついた舌を舐ってぐずついた甘さを飲み込んだ。凝縮された糖分よりも女の血反吐のほうがずっと、味蕾を塞いで仕方なかった。男は利口なので、本当までを遠回りするとゆるい幸せが続くと学んでからはお喋りが上手になった。茶番狂言や飯事に相思相愛と題目を付ければ、一挙手一投足が愛情表現になる。パンケーキを口いっぱいに詰めた女を愛でていたら昨晩の傷を思い出した。ふわふわを含んでふくふくの頬に触れたくて、治っていれば喜んで、治っていなければ悲しむだけだった。それを女が、ほんのすこし考えて、あからさまに尖らせた唇でいじけてみせたのだ。男は正しく甘えだと理解して、胸に広がる歓喜に従った。
女が皿の半分まで頑張って、ここからは無茶の範疇ね、なんて気を引き締めた瞬間。遠くのほうから引き攣れの悲鳴が響いた。カトラリーを握りなおした男は白飛びした虹彩を隠すように目を細め、女の艶やかな唇を見つめる。山の一番上から切り崩して、ちんまり一口分にすると、たっぷりのジャムを乗せて差し出す。
「んあ」
「ちいちゃいお口だなあ」
「つぎはバターがいいわ」
「はあい」
縺れた足音が行きつ戻りつ、戸惑いを示しながらも徐々に近づいてくる。バター、お次はジャム、それからバター、そのまま食べて、最後の一口はどちらも贅沢に。口いっぱいに頬張って、ごくん。
ばたん。
「い、怡陽! お祖母様が、そこで、ね、いはる? なにを、してんの? なに、そいつ」
ふうふう、ちょっとおかしな呼吸を宥めて意を決する。
「もう一枚、食べさせて」
きりりと凛々しい女にときめきながら、男は多少なりとも意識を他所に向けた。忠実でありたいが、盲目ではいけない。男は最愛を守らなければならないので。記憶の彼方から、廊下に転がった蛆の餌場を引っ張り出して、口振りからこれが姉だと断定する。パンツスーツ、ジャケットに重みは感じないし、ポケットも膨らみは薄い。鞄もなく、テーブルや食器棚からは距離があって、両手を擦り合わせて落ち着きがない。それに視線が合わない。男に言及したにも関わらず、焦点は女にピタリと合って動かない。凶器の類を掴む前に殺せる。警戒は解かずに、だが過剰に気にする必要はない。侵入者に鋭い敵意を刺したまま、女の狭い肩を抱いて身を寄せた。暖かな空気が一目散に逃げていく。
女は「甘やかしてくれるのね」なんてくふくふ笑って、次いで突っ立ってる人間にちょいと視線をやって、知ってる顔だ、と認識した。それだけだった。女にとっていま重要なことは、男の愛情をより多く取り込むことに他ならない。よって他者の存在は不純物となり脳内から排除された。
「っやめてよ、怡陽」
寝入りの耳元に羽虫が飛んだような不快感に堪らず眉根を寄せた男は、カトラリーを手放して膨れた頬を揺らす女を膝に抱えた。くにゃっと力を抜いて委ねてくる女の頭を撫でりこ撫でりこ。傷つけることを恐れずに触れるようになったのは、傷さえ慈しむ女だと知ったのと、女が爪の先までぴかぴかに手入れしてくれるから。ささくれのない指先の快適さ。男の些細な不快を許さないでいてくれる女だ。だから、もちろん姉のことも。
「邪魔よう」
女は、姉の見開いて光を受ける目玉に驚いた。薄茶けた土塊の、すぐにでもひび割れそうなざらりと乾いた質感。鏡を覗けば絢爛たる珠と見つめ合ってきた女にとっては路傍の石と変わりない。女の姉とするにはあまりにみすぼらしい。父と祖母は老いさらばえて見苦しくなったのだと勘違いしていた。これらはそういう生き物なのか。碌に顔を合わせもしなかったから、気が付かなかった。
それから、姉はキーキーひしゃげた蝶番みたいに喚いて、いくつかのことをさも重大な事件かのように告げた。女はぼぅっとしながら、髪を滑る大きな手に感謝していた。形を整えるような、僅かに圧を感じる手つき。これがなければ今頃に皿の一枚が割れていたかもしれない。かしゃん、と割って、えいって。手が切れていたかも。たかが姉の命一つに釣り合わない大怪我をするところだった。一頻り語って満足したらしい姉の要件を纏めれば、なに大したことのない話だ。
「そっか。御父様も御祖母様も死んだのね」
「それで、怡陽が必要なのよ」
「はるちゃんを載せンな」
量られた。男の脳内はそれでいっぱいになった。死体のもう一方に女を乗せて、針を読みやがった。侮辱だ。女は無二の光、質量を持たない絶対なのだ。それに、飛永怡陽の対にあっていいのは河津風祐そればかりだ。ぎゅーっと女を抱きとめた。腕がもう一本あればナイフでも投げて殺していた、いや、女を囲うのに精一杯だったろうな。
「あら。羽根一枚で事足りるでしょうに、どうせ貪り喰われるわ」
女には見えた。男の頭上にクエスチョンマークが浮かんだのを。たぶん現実だったんじゃないかしら。「エジプト神話よ」と囁いてあげれば、知らないなあ、という顔をしていた。知らなくていい。女はこんな煩わしい物言いはしない。
「怡陽にも遺産を相続するためよ、遺言書がない状態で事を進めなきゃ。飛永家の次女がどんな扱いを受けてるかなんて周知の事実だし、死出虫に集られるのは嫌。かわいい妹には虫なんか似合わない」
「腹立つなあ!」
はるちゃんに出逢った路地裏を思い出した。ワンピースを闊歩する虫、似合わない。ああ全くの同意見だ。そのくせこの姉は、女がそうあることを許した。今になって、死体に集る口さがない虫を遠ざけようとしている。
「どうして今更なのかしら?」
「前の私は、飛永家のものだったから。怡陽は大事にされてなかったでしょ。私は怡陽が大好きだけど、飛永家の者としては大事にするべきじゃないんだと思ってた」
「だいすき?」
姉の口から出た虚偽を、初めて聞く言葉だわ、と思った。既知のそれと比べるのも烏滸がましいほどに平坦で、男の激情に耽溺した心には触れることなく通り過ぎた。上滑りする語彙をつらつらと、よくも絡ませずに吐けるものだと舌の回りに感心する。これが飛永か。糸を引くような粘度の大きい苛立ちを覚えたのは生まれてこの方初めてだった。男の前で血筋を誇って恥を晒さないで欲しい。
「勿論! 生まれた時から知ってる、私の妹。ずっと、変わりなく、妹なんだから、愛してる」
得も言われぬ嫌悪、それに付随する吐き気が余程に鬱陶しい。男の手作りのパンケーキが詰まった胃袋の、何が不満かと己に叱責して、これこそが愛だと腑に落ちる。
「それ愛じゃねえよ」
「畜生に何がわかる!」
「はるちゃんが俺をあいしてるってこと、なんでわかンねえの?」
わかってたとして、なんでその物言いができるのか、男は首を捻るばかりだった。それから、偽悪的な行動を取ろうと決めた。畜生という謗りに心が痛むのは罵倒だからじゃない、不快なのは飛永怡陽を軽く扱われたこと。痛みを宥めてほしい、いまこの瞬間に、目の前で。その意味を、女は理解してくれるし、その上で嬉々としてそう振る舞ってくれる。男はそれを理解している。
「俺さ、傷ついた。はるちゃあん、慰めてくれえ」
「ふゆ、わたくしの風祐、王様‥‥あ。泣いてしまうのね」
「ウン」
「そうなの……」
女は指先を揃えもせずに男の頬にしっとりと滑らせる。同じ目玉で世界を見る男が愛しい。互いの言葉と心と、融かして身の内に湛えて、等しい温度の生き物になったのだ。男が自覚的に、立ち居振る舞いでもって意思表示をするなんて! 出会ったばかりの男なら、明け透けな暴力で一思いに殺して終いにしただろう。そういう素朴な手段を選ばないのは、殺すよりもまず、その手で撫でてほしいと女が望んでいたから。いまだって、離さないでほしいと望んでいるからここにいる。武骨な両の手で女をぎゅっと抱えて、けれどやっぱり男は武力なのだ。見て、学んで、選べるようになっただけ。
「これが愛だから、それが愛じゃねえってわかるンだよ」
「愛が一つだとでも思ってるの?」
「きもちわりいなあ! はるちゃん、あいつやっぱりわるいやつだ」
本当は今すぐにでも息の根を止めてやりたいが、なかなかどうしてそういうわけにもいかない。男は腕に血管が浮かぶほどに力を込めて耐えた。この腕を少しでも緩めれば、あるいは殺意の行使のために動かせば、抱えた愛情の権化が肉親殺しの汚名を引っ被るだろう。その前にカトラリーでも投げつければ、いいや、万が一にもはるちゃんに当たったら? やっぱり、このまま抑え込んでおこう。ぎゅっぎゅっ。女は上出来の頭からあらゆる躊躇いを捨て去ってスッカラカンにした。それから理性を削いで、幼心にあらゆるものを託した。じた、ばた、んぎぎ‥‥! あとほんの少し隙間があれば身体を捻って逃げ出せる、のに? ふざけるな。本性が単調な思考を押し並べて殴りつけて理性を引きずり出す。男の愛情から”逃げ出す”だなんて、あってはならない。不埒者めが。慣れないことはするものじゃない。ちょいと視線を上げれば降り注ぐ気遣わしい眼差しが安堵にゆるんだ。沈み切らなかった幼心がはしゃぐ。わたくしの風祐くんだいすき。
「今日もいっとうすてきだわ、風祐くん」
「ン? ウン、はるちゃんのだからなあ」
それで、アレは殺していいのか? ダメ? ダメそおだ。理性のある女は男の関心と愛情の行為を求めるし、理性のない女は肉親殺しを望む。状況は一進一退の停滞、殺意は動機を余らせて遂行し倦ねている。勝手に出ていきゃいいのに、突っ立ってンなよ目障りだ。男は情操教育の真っ只中だから、自分の心が何に騒めいているのかと向き合って、あんまり受け入れたくない事実を手にしたりした。俺のはるちゃんが俺に向けるはずのない激情を、一身に浴びる”肉親”という存在。嫉妬してる。だっておかしい、俺はいはるのまるごとをもらったすてきな王様で、飛輪を抱く永久の権利を得たただ一人なのに。はるちゃんは俺のこと殺そうとはしないのに!
「ぐぎゃっ」
「風祐くん?」
呆気にとられた女は突然に寝床のラグを奪われた犬のような顔で男を見上げていた。しんじられない。風祐くんが、わたくしのことお膝から降ろした……わたくし降ろしてほしくなんてなかったわ。ごんっ、どさ。ぎゃあぎゃあ。烏骨鶏だったのね。それでお仕舞だった。あたらしいフォークを出さなくちゃ。風祐くんきっと、ダーツがお上手ね。
「ひどいことよう」
「ごめンなあ」
口角をぐにっと下げた男の顔を見て、あ! と思って、「あ!」と言った。
「許されると思ってるでしょう」
「思ってる」
「すなお!」
男は目の前でいじける乙女を颯爽と抱え上げて暖かなキッチンから出た。ひょいと障害を乗り越えて、ふわりと舞った髪を愛でながら。鼻腔に残る小麦とバターと紅茶の香り、幸福は途切れた。男の罪だ。許しを乞おう。暴力を打開策とした身勝手を許される自信があった。やっとのことだ、まるごともらったのだから! あまりにも現実味のない現状に事実を見誤った。約束事は飛永怡陽の尊厳を取り戻すことで、それを為して初めて権利を得るのに。ベッドの真ン中に置いてもらって、手ずからパンケーキを食べさせてもらったから、愚図な頭が勘違いしたのだった。それで、これからは胸を張っていい。ぐるぐる考えても歩みは止めず、乱れたままのベッドを目指した。
腹立たしい。女の思考を支配する全てがそこに帰結する。ふと、仰いでばかりだと気が付いた。このままじゃ額の形を忘れちゃうわ。
「降ろしなさいな」
「…………どおしても?」
黙って目を瞑って、男の顔を思い浮かべる。顎先から頬骨に繋いで、薄い唇を引き、尾翼の膨らみから眉間まで、眉に沿って、瞼の丸みを撫でた。悲しいことね、額の凹凸はどんなだったかしら。瞼を開いたとき、同じ形をしていなかったら?
「降ろす、おろすからあ、怒ンないで‥‥」
「許しちゃないわ」
べったり抱き着かれてくるしい、喉がきつく締まるほど顎を持ち上げてやっと顔が見えた。ふぅん、そういうことなさるのね。「離しなさい」自由ってすてき。胸倉を掴んで顔を寄せた。鼻先を擦りあってみれば霧を閉じ込めた瞳に自分が映る。一歩「どこいくの」二歩「はるちゃん、まって」三歩「おいてかないでよお」、指先に辛うじて引っ掛かる布地をしっかり抓んで腕を下した。すっかり前屈みになった男がその場でおずおずと膝を折るのを認めて、それから半歩だけ近づいて前髪を撫でつける。
「かわゆいお顔」
「エ、っと、俺かわゆいけど、許されない?」
男に媚びを売るという概念は存在しない。女が嫌悪していることを男が身に着けるわけがない。よってこれは素直な反応で、だから女は辛抱ならないのだ。吸って、吐いて、飛びついた。あちこちに跳ねる髪をわしゃわしゃとかき混ぜて、かわゆくてしょうがないお顔をもっちゃもっちゃしてやった。それからあにあに鼻だの頬だの甘噛みして、へろへろになった男をぎゅぅっと胸に抱く。このまま肋骨の裏側に閉じ込められないかしら。ふかふかの肺に熱い心臓、きっと居心地がいいと思うの。口を半開きにして目を白黒させてるのもあどけなくてかわゆい。食べちゃお。
「いたあい」
お利口にしたら降って湧いた愛撫に従順に喜んでいたのに、同じ温度で頬をしっかり噛まれた。血は出ていないがほぼ咀嚼だ、不意にやられるととても痛い。はるちゃんは噛むの好きだなあ。食べたいなら食べればいいのに。階段の踊り場、壁に穴が開いたような窓から真白い陽が射している。女の顔は逆光で暗い。それがどうして眩いのか、男はとうに知っている。視線で皮膚が爛れる、脂肪が溶けて筋肉が崩れる。骨は炭になって、やけて、やけて、灼けたら灰になって。そうなったら女は泣いてしまう。灰と涙は混じって粘土になって、捏ねて元通りにしてくれる。男の正しい形を知っているのは女しかいないのだ。許されないまま愛されること、いまはなにより嬉しい。あとすこししたら泣きたくなる。恨まれるのも憎まれるのも嫌だ、でも一番がいい。
そのために殺した。女は目の前にあるものをそうと認めてしまうから。憎悪の対象を憎悪で上回るのは不毛な努力だ、男は戦い方を選べる。現状の一番がいなくなれば繰り上がる。男が一番になって、許してもらって、憎悪は空席になるのだ。
「ごめンなさい」
「なんのことかしら」
「はるちゃんを、勝手に膝から降ろしたこと。嫉妬してるって言えばよかったンだ」
「……しっと、してらしたの?」
「ウン」
へぇ、そう、ふぅん、つま先をもじもじ擦り合わせる女は華奢な首まで真っ赤だった。比べるまでもなく特別を自負する男が、あの木偶と自分の何かを比べて嫉妬したらしい。女を一番に据えた男が女の一番になるための身勝手を、どうして怒っていられよう。いじらしくも堂に入った甘えは女の神経をとっかえひっかえ混線させ思慮分別を奪うのだ。単純化された知性は男がいかに愛らしいのかを滔々と語る。わかっていてやっているのだ、それが好き。揺るぎない愛情を理屈で補強したかっただけのこと。本当に怯えて不安なら、女とともにどこかの部屋に籠城して言葉を強請っただろう。それから扉の向こうで騒ぎ立てる狼藉者に耐えかねて、過ぎた威嚇の結果に静穏を得たはずだ。そうはならなかったのは、偏に河津風祐が飛永怡陽の愛を自己愛の根源にしているから。
「ゆるしてさしあげるわ」
濁りのない声に満足した男はへちょ、と滴るような笑顔を浮かべて女に甘えた。俺はゆるされるンだ、愛されてるから。
「なあ、はるちゃん」
「なぁに、風祐くん」
「いはる‥‥い、はる……」
女の瞳にはかえるの如き醜男がいっぱいに映っている。絶美の一端たる手指が男の頬を滑る。絡め取って強く握った。立ち上がると同時に細腰を支え思いのままに一回転。無邪気に喜ぶ女を陽光から隠した。男の影にすっぽりと収まった女は上気した肌を冷ますつもりもなく、灼熱を孕んだ眼で男を見つめ口付けを誘った。
「わ、たし、の……かわい、い、いはる」
「言って? 俺、ほら、察するのにがてだ。甘やかしてほしい」
「おね、ぇ、ちゃん、よ……いはる、いも、う、と……」
「暇なく口付けをちょうだいな」
「愛し、て」
なんだかそれがとっても婀娜っぽくって、男はそれがからかいだとわかっていても、ワワワ! となってしまったのだった。はるちゃん……ずるだ。なんとなく負けた気持ちになったから潔く不格好な口付けを贈った。むぢゅ。
「あ、あぁ!!」
ごろごろ、どすん。女は眉を顰めて、男が親指ですりすり伸ばした。烏骨鶏のおばけが出たらしい。「事故だ」肺の震えだけで笑った男がそう呟くから、この薄暗いお屋敷の全てが嫌になってしまった。陰気臭いのって不愉快だわ。食べ損ねたパンケーキが萎んで朽ちていくのも、蛆が羽化するのも、おばけが出るのも。ドレスもワンピースもネグリジェも、イヤリングもバングルもネックレスも、パンプスもミュールもローファーも。カーテンの柄もシーツの手触りもシャンデリアの形も嫌い。
「燃やす?」
「それって、あはは! すてき!」
煌びやかなショーケースのある店よりも、窓から洩れる光の優しい店がいい。はるちゃんは重たいソファーに使われるもったりした生地よりも、空に透けるくらい軽やかな方がよく似合う。靴だって本当は、爪先が尖ってないのがいい。人差し指から小指まできちんと並んで、親指がそっと寄り添うあの足が、狭いところに押し込まれているのは悲しくなる。はるちゃんが俺の服ばかり見ていて時間があまりなかったから、大きさと色だけで選んだけど納得はしていなかった。歩かせたくないと思う靴だった。この屋敷には、そういうものだけがある。
「証拠隠滅ってどおしたらいい?」
「なんにも残さなかったらいいわ」
「死骸って燃やしたらなにが残る?」
「骨、特に歯。歯の形は人それぞれだから、そうね、砕きましょう」
「それだ、はるちゃんは賢いなあ」
「燃料と死骸をキッチンに運んで火をつけて、扉を閉めたらオーブンになるわ、っふふ、あははは!」
笑い転げる女は無邪気で、自分の言葉を反芻しては新鮮な気持ちで感心した。オーブンが備え付けられた部屋をキッチンと呼んで、わたくしたちはいまからキッチンをオーブンにするのね。内包していたものが大きくなって取って代わるのがどうしてか余程におかしかった。男はいよいよ涙まで転がした女の髪に指先にと戯れながら順番を考えていた。燃料を用意するのが先だ、それから廊下で羽虫の楽園になってる祖母と階段下の死に損ない事故死した姉の歯を抜いてから砕いて、絨毯で包んでキッチンに運ぶ。燃料ぶっ掛けて、風呂入ってから着火。汚れたままだとはるちゃんに触れないし。ウン、これで完璧。
「納屋にいけば発電機の燃料と工具があるわ」
「なんで知ってンの?」
「折檻部屋だったの」
「絶対に何もかもを燃やし尽くして見せるからなあ!」
「たのしみ!」
浮き足立った女を背負って廊下を駆け抜ける。勝手口から裏手に抜けて、納屋の錆びついた戸を蹴破った。一刻も早く離れたいが、焦って女を振り落とすわけにもいかない。邪魔なものは足蹴にしながら隅にあるガソリン携行缶と落ちてたトンカチを拾う。屈んで手を伸ばした拍子に支えを失った女の脚がぷら、と落ちかけて肝が冷えた。
「はっ、はるちゃん! いま、いまだけでいいからあ、俺のお腹にぎゅってしといて!」
「こうかしら」
「ありがとお」
よいしょ、体勢を整えて急いで安全な場所へと引き返す。こんなとこに居られるか! キッチンの前にじゃぼん、と携行缶を下ろしてから椅子を運んで女を座らせた。男にはこれから大仕事が待っている。額を差し出して口付けを貰った。「いってきまあす」声を張り上げて、ア忘れ物した。いそいそと流しから手拭いを取って向かうは階段下、まだ臭くない方から手をつける。釘抜きのほうを口に差し込んで、ぐい、と下顎を外した。
「うぇえ! きもちわるっ! うわ、うわうわうわ、やっぱこいつきもちわりい!」
はるちゃあん、こいつきもちわるいよお、えぐ、ぐす……ハハ! さっさとやろ。人でなしは本当に人でなしだったのかもしれない。俺は蛙の化け物もどきの人間だけど、こいつは人間もどきの人でなしだ。血塗ろの口内に手拭いを突っ込んで鎚を振り下ろす。前歯が外れたら釘抜きの先で上顎をがりごり、いち、にい、さん、しい、ごお、えーと、いっぱい。骨が見えるころには全ての歯が外れた。一個ずつ取り出して砕こうとしたけど、ばふっと絨毯に沈んで駄目だった。先に剝がしときゃよかったな。廊下の真ん中あたりに切れ目を見つけてベりべり、接着剤がきつくて困る。床材はタイルだった。思った通り硬い素材で都合がいい、剝がれにくいところはトンカチで殴ってくっついてるタイルを粉砕した。ところどころ下地のモルタルまで露出してる、ここなら歯も砕けるだろう。がん、がん、ごつ、きーん、がん、手が痺れてくる。上手いこと歯だけに当たれば望み通り粉々になった。あと三三本。それから三十二本、あっちはそんなに残ってないかもしれないけど。代わりに蛆が嵌ってたら手叩いて笑っちゃうかもなあ。
「ひ、っひ、ははははは! ひい、ひはははっ!」
「ふふっ、あはは! あっははは!」
女は遠くから響き渡る哄笑に合わせてたふたふとステップを踏んで遊んでいた。愉しそうね、風祐くん。わたくしとっても清々しいの。うふふ、あはは! スピン、リバース、ホイスク、シャッセ、いつかワルツを踊りましょうね。男の長い手足は優雅な三拍子に映えるだろう。気取って顎を上げて視線を絡めればきっと腰が抜けるほど艶やかで、脱力した身体を柔らかくリードしてくれるはずだ。目を開けて夢を見る女の脳内には、青々とした芝生の上で裸足を晒し戯れる二人の幻想がゆれていた。